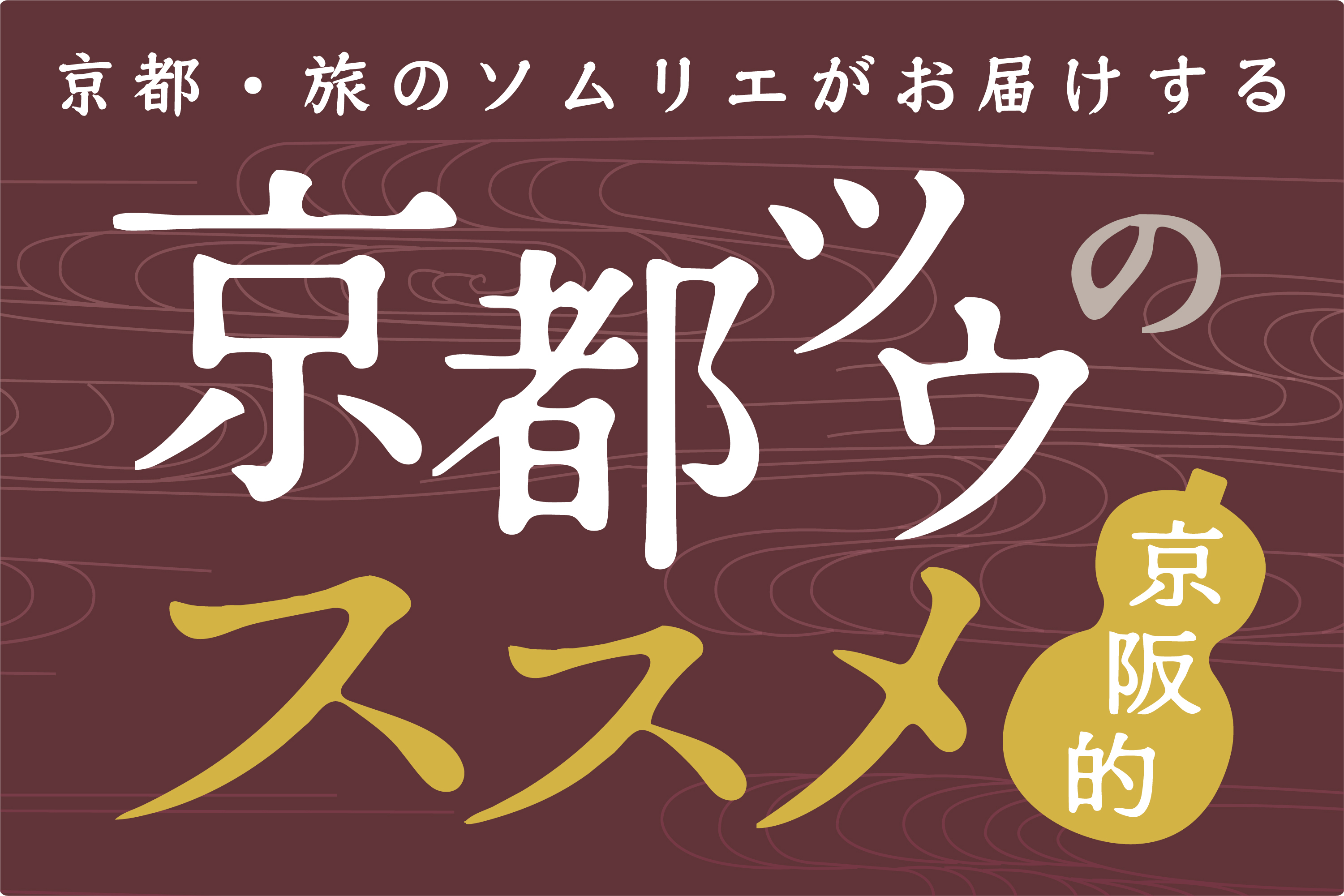
第206回
京都の酒
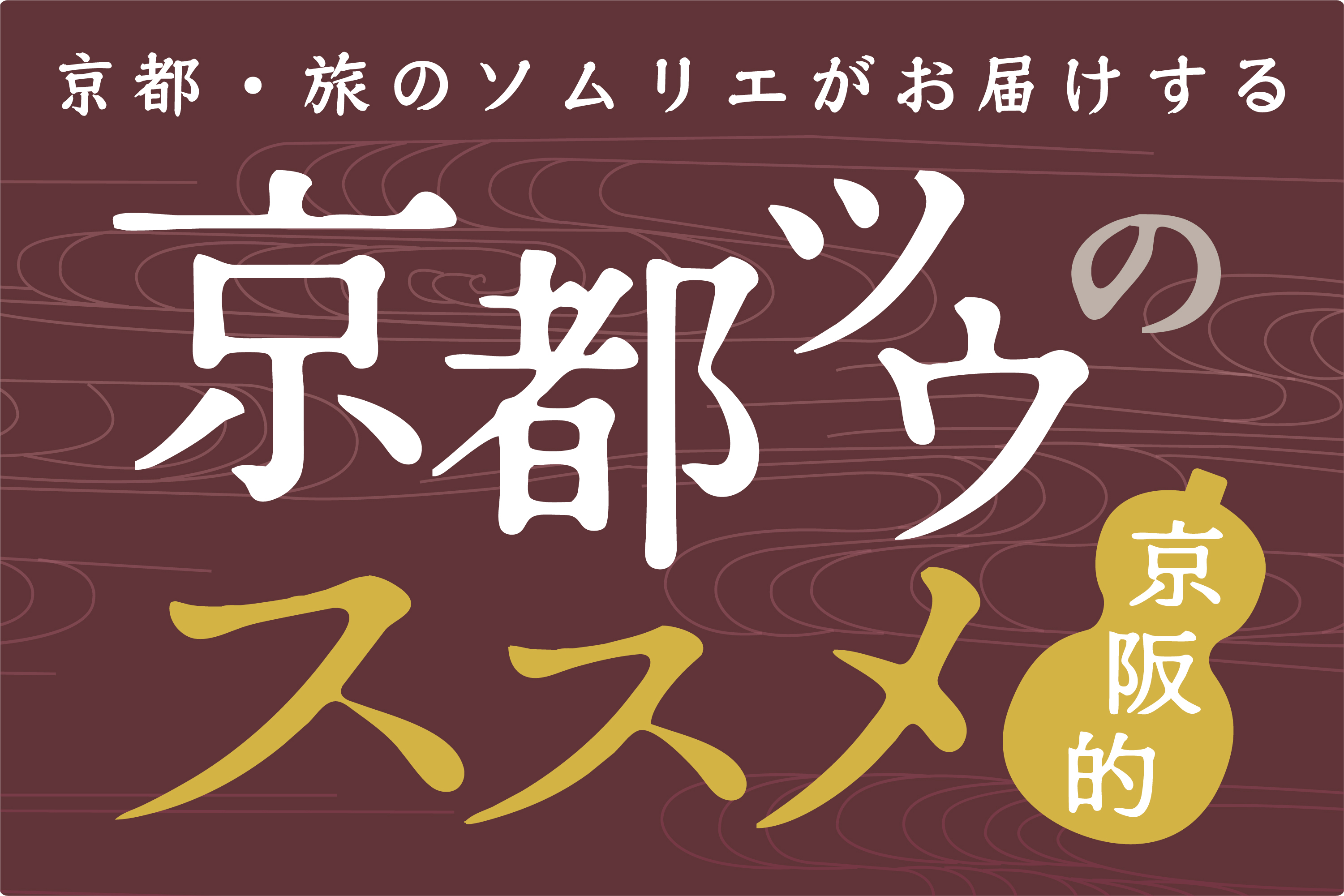
第206回
京都の酒

月桂冠内蔵酒造場(写真提供:月桂冠)
京阪的京都ツウのススメ
第206回 京都の酒
平安時代から続く酒どころ京都
名水に恵まれた京都は、全国有数の酒どころ。
千年以上にわたる歴史を持つ京都の酒について「らくたび」の若村 亮さんがご案内します。
京都の酒の基礎知識
其の一、
かつて平安京には酒造りを行う役所があり、宮中用の酒が造られていました
其の二、
酒造りが盛んになった室町時代の京都の市中には、多くの酒屋がありました
其の三、
今も、京都の名水や京都生まれの酒米を使った酒造りが行われています
宮中の行事に使われる酒を醸造
日本で米を原材料とする酒を造り始めたのは、稲作が伝来した縄文時代から弥生時代と考えられています。平安時代には宮内省に所属する造酒司(みきのつかさ)という役所が、酒の醸造を行っていました。宮中行事などを記録した法典『延喜式』には、天皇に献上する御酒(ごしゅ)や官人のための頓酒(とんしゅ)などの製法が記されています。宮中で9月9日に行われていた重陽(ちょうよう)の節句では、厄除けを祈願し、不老長寿の象徴である菊の花を浮かべた菊酒が振る舞われました。
水に恵まれた京都は昔も今も酒どころ
豊富な地下水に恵まれていた京都の市中では、鎌倉時代から酒造りが広まり、室町時代に最盛期を迎えました。安土桃山時代に入ると、豊臣秀吉が伏見城を築いた京都市南部の伏見で酒造りが盛んになりました。桃山丘陵からの伏流水が湧く伏見は、江戸時代初期には宿場町や港町として栄え、酒造家も83軒を数えました。今も、京都府の日本酒生産量は全国2位を誇り、京都市内の酒蔵でも丹精込めた酒造りが行われています。
京の酒 今昔
平安京で造られた酒や、酒と神社の深い関わりなど、京都と酒の歴史をたどってみましょう。
平安時代の酒造りの役所

地面の四角い線と丸い模様が倉庫の柱の跡
現在の生涯学習総合センター・京都アスニー(中京区)の敷地には、かつて宮中用の酒の醸造や管理を行った役所・造酒司がありました。原料の米や出来上がった酒を保管したと考えられる高床式倉庫の跡が見つかっています。
造酒司では、天皇が収穫を感謝する新嘗祭(にいなめさい)に供えられた白酒(しろき)・黒酒(くろき)など、宮中で使われる何種類もの酒を造りました
酒屋が増えた室町時代
室町時代、京都の市中には酒の醸造や販売を行う酒屋が340軒以上もありました。中心部では、地中に酒甕(さかがめ)を据え付けた穴や井戸の跡など室町時代の遺構が発見されています。
室町時代の公家は、10人ずつ2組に分かれて3種類の酒の利き酒を行う十種酒や、グループで酒を飲む早さを競い合う十度飲(とたびのみ)などを楽しんだそうです
京都の名水や酒米で醸(かも)す酒

月桂冠大倉記念館(写真提供:月桂冠)
名水
京都の酒造りを支えるのが、京都盆地の地下水や桃山丘陵の伏流水です。特に伏見は、地名が伏水(ふしみず、地下水の意味)に由来すると言われるほど水に恵まれ、今も多くの蔵元がこの伏流水を酒造りに使っています。

酒米
京都生まれの酒米である祝(いわい)。精米歩合の高い吟醸酒などに向いており、きめ細やかでやわらかな味わいの酒になると言われています。これは伏見をはじめ京都府下の蔵元だけで使用されています。
酒造りと神社

松尾大社/西京区
酒造りの技術を持つ秦(はた)氏が松尾大社を氏神としていたことから、酒造りの神様として信仰を集めるようになりました。御神水「亀の井」の水を酒の仕込み水に加えると、酒が腐らないと言われています。

北野天満宮/上京区
室町時代、北野社(現・北野天満宮)は、酒造りに必要な麹(こうじ)の製造や販売を担う北野麹座として幕府に認められていました。そうした神縁から酒造会社からの崇敬を集め、毎年5月の献酒祭では京都をはじめとした関西の酒造から新酒が奉納されます。
京の酒造り いろいろ

佐々木酒造/上京区|代表銘柄:聚楽第(じゅらくだい)
千利休ゆかりの名水を使用
1893(明治26)年創業。千利休が茶の湯に使ったと言われる「銀明水」と同じ水脈の水を仕込み水に使用しています。代表銘柄の「聚楽第」は豊臣秀吉の邸宅の名前。酒蔵が、聚楽第の南端に位置することにちなんでいます。

松井酒造/左京区|代表銘柄:神蔵(かぐら)
鴨川のそばで酒造り
現・兵庫県香美町で1726(享保11)年に創業。江戸時代後期に現在の京都市中京区に移り、大正時代の路面電車開通に伴い現在地に移転しました。「御所三名水」の流れを汲む「洗心甘露水」で酒を仕込みます。

北川本家/伏見区|代表銘柄:富翁(とみおう)
舟宿の主が造った酒が評判に
伏見の豊後橋(現・観月橋)の近くで舟宿を営んでいた初代鮒屋四郎兵衛は、酒造業の免許制が始まった1657(明暦3)年には既に酒造りを行っていたと伝えられています。客のために造っていた鮒屋の酒は評判となり、大坂や江戸にも運ばれました。
日本で最初に名付けられた酒の銘柄が「柳の酒(柳酒)」です。室町時代に京都の酒屋が造り、公家が贈答品として使うほど人気がありました
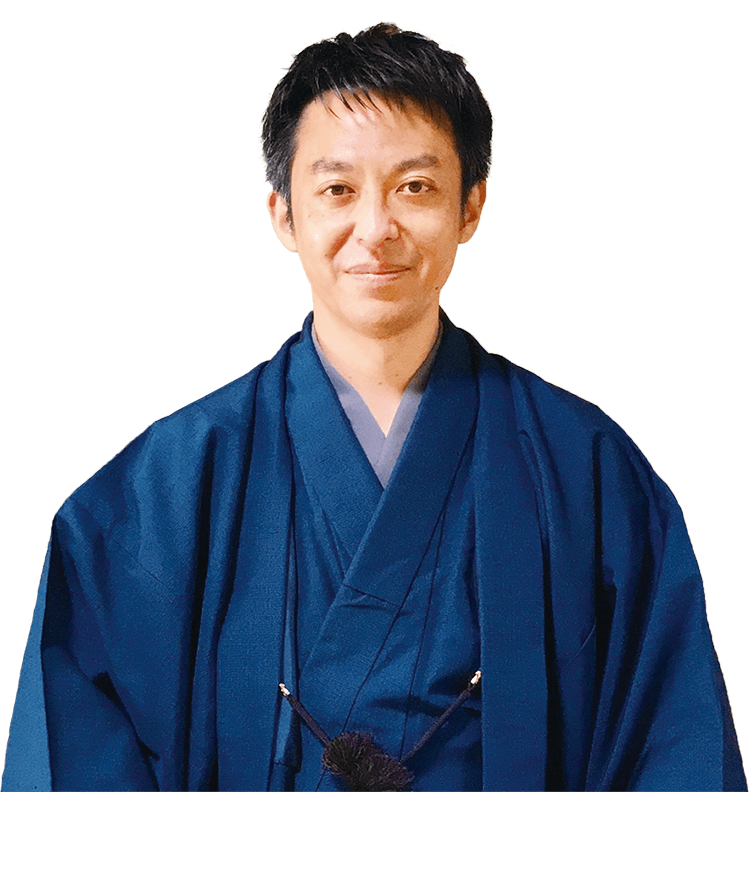
ナビゲーターらくたび 若村 亮さん
らくたびは、京都ツアーの企画を行うほか、京都学講座や京都本の執筆など、多彩な京都の魅力を発信しています。
制作:2025年10月




