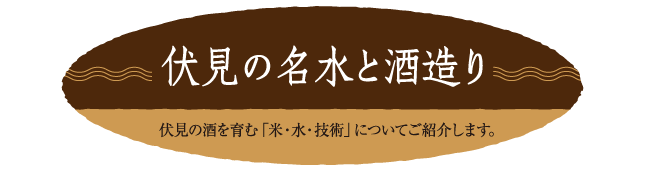京都ツウのススメ
第三十一回 伏見の酒
![[名水が育む銘酒 伏見の酒造り] “日本酒の産地として全国的に知られる伏見は現在も様々な銘柄が生み出されています。 名水が育む伏見の酒についてらくたびの若村亮さんがご案内します。](/navi/kyoto_tsu/img/201011/main.jpg)
- 其の一、
- 京都府は全国2位の日本酒生産量を誇り、中でも伏見は日本有数の酒どころです
- 其の二、
- 伏見では地下水が豊富なことから、酒造りが発展しました
- 其の三、
- 伏見の酒は、きめが細かくまろやかな風味が特徴です
受け継がれる酒造り
三方を山に囲まれた京都盆地は昔から豊富な地下水に恵まれてきました。平安時代には宮中に造酒司(みきのつかさ)という専門の役所が置かれ、酒造りの技術が磨かれてきました。鎌倉時代には酒を造って売る店が登場、室町時代には洛中に約340軒もの店があったと言われています。その後、貴族の衰退とともに酒造りの拠点も南下、豊臣秀吉の伏見城築城を機に伏見での酒造りが盛んになりました。
酒造りを支える名水
京都市の南部に位置する伏見は、その地名を伏水(ふしみず=地下水)に由来するほど、名水に恵まれた土地として知られてきました。この豊富で良質なわき水を使って発展したのが酒造り。日本酒は原料である米こうじと酵母を用い、ミネラル分を適度に含んだ水をふんだんに使って長い時間をかけてゆっくり発酵させるため、きめが細かく、口当たりのやわらかな酒ができあがります。伏見の町では今も清冽な水に恵まれており、現在20数社ある蔵元の多くが名水を使い、京都を代表する銘酒を造り続けています。
水と並び、酒の味を左右する酒米(さかまい)。伏見ではかつて京都府特産の「祝(いわい)」が使用されていましたが、稲の背が高く倒れやすいことから生産が一時中断しました。しかし、1991(平成3)年に伏見酒造組合の働きかけにより品種改良が重ねられ復活。「祝」を使った酒は淡麗な味と独特の香りを特徴とし、伏見を中心に京都の蔵元で造られています。

齋藤酒造の「英勲」をはじめ、現在伏見では11社が「祝」を使用したお酒を造っています

かつて伏見の町には七名水(七ツ井)と呼ばれる井戸がありました。このうち白菊水、常磐井水、竹中清水、御香水の4つは現在もわき出ており、日本酒蔵元である山本本家では白菊水が今も酒造りに使われています。花崗(かこう)岩が多くを占める伏見の地層からわき出す水は、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を適度に含んだ中硬水。この中硬水は、硬水を使った時に比べ酵母の発酵が緩やかになることから、伏見の酒の特徴であるきめ細やかな優しい味わいとなります。

京都では、奉公人が独立する際には、主人から長のれんを与えられるという習わしがありました

1909(明治42)年、従来の伝統的な酒造りに科学技術を導入するため、酒造メーカー・月桂冠が「大倉酒造研究所」を設立。酒質の改良を行うとともに、樽(たる)詰め酒全盛の時代に酒の腐敗を防ぐ瓶詰め酒をいち早く開発。全国に伏見の酒が広まる基礎を築きました。また1961(昭和36)年には日本初の年間を通じた酒造りが可能な四季醸造蔵を完成。伏見の酒を、日本を代表する銘酒へと育てあげていきました。

明治末期に旧国鉄の駅で売り出された「コップ付き小びん」は月桂冠の名を全国に広めるヒット商品となりました

駅売りの「コップ付き小びん」
(写真提供 : 月桂冠大倉記念館)
酒米「祝」を使い、華やかな香りと繊細な味わい。冷やで楽しむのがオススメです。720ml/5,250円(齊藤酒造)
油長限定発売で、誰でも飲みやすい中口。穏やかな香りとキレの良さが特徴です。720ml/2,045円(山本勘蔵商店)
昔ながらの「きもと造り」という製法で醸造したお酒。豊かなうまみのある奥深い味わいが楽しめます。720ml/1,365円(招徳酒造)
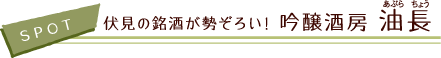
伏見にある19の蔵元の銘柄がずらりと並ぶ酒屋さん。常時80種類以上そろうという日本酒の中から、店内のカウンターで飲み比べできる「お猪口3種飲み比べ(付き出し付き)」は650円から。伏見の酒入門にもってこいです。
- 10時~22時 火曜(祝日を除く)休業
※11/23(祝・火)は18時まで - 075-601-0147
- 伏見桃山駅下車 西へ徒歩約5分

協力/伏見酒造組合、月桂冠株式会社

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団
- 第二百六回 京都の酒
- 第二百五回 京都の公家(くげ)
- 第二百四回 自然豊かな山里 大原
- 第二百三回 京都と七夕
- 第二百二回 幕末の京都と藩邸
- 第二百一回 京都と水
- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺
- 第百九十九回 京都画壇と美人画
- 第百九十八回 京都の山
- 第百九十七回 京都と豆腐
- 第百九十六回 南座と歌舞伎
- 第百九十五回 京都の巨木
- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)
- 第百九十三回 秋の京菓子
- 第百九十二回 京都の植物
- 第百九十一回 京都の風習
- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)
- 第百八十九回 京都と魚
- 第百八十八回 京都とお花見
- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地
- 第百八十六回 京都の地ソース
- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地
- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い
- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)
- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば
- 第百八十一回 京都の中華料理
- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都
- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子
- 第百七十八回 京都と徳川家
- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)
- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)
- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)
- 第百七十四回 京の難読地名
- 第百七十三回 京の縁日
- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)
- 第百七十一回 京都の通称寺
- 第百七十回 京都とキリスト教
- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り
- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え
- 第百六十七回 京の城下町 伏見
- 第百六十六回 京の竹
- 第百六十五回 子供の行事・儀式
- 第百六十四回 文豪と京の味
- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理
- 第百六十二回 京都のフォークソング
- 第百六十一回 京と虎、寅
- 第百六十回 御火焚祭
- 第百五十九回 鴨川の橋
- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)
- 第百五十七回 京都とスポーツ
- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見
- 第百五十五回 京都の喫茶店
- 第百五十四回 京の刃物
- 第百五十三回 京都の南蛮菓子
- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)
- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉
- 第百五十回 京のお雑煮
- 第百四十九回 京の牛肉文化
- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)
- 第百四十七回 明治の京都画壇
- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)
- 第百四十五回 ヴォーリズ建築
- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)
- 第百四十三回 京の人形
- 第百四十二回 京の社寺と動物
- 第百四十一回 鳥居(とりい)
- 第百四十回 冬の食べ物
- 第百三十九回 能・狂言と京都
- 第百三十八回 京都と様々な物の供養
- 第百三十六回 京都とビール
- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)
- 第百三十四回 精進料理
- 第百三十三回 明治時代の京の町
- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物
- 第百三十一回 京の調味料
- 第百三十回 高瀬川
- 第百二十九回 蹴鞠
- 第百二十八回 歌舞伎
- 第百二十七回 京都に残るお屋敷
- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]
- 第百二十五回 京の学校
- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり
- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>
- 第百二十二回 京都とフランス
- 第百二十一回 京の石仏
- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)
- 第百十九回 生き物由来の地名
- 第百十八回 京都の路面電車
- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納
- 第百十六回 京の歴食
- 第百十五回 曲水の宴
- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)
- 第百十三回 パンと京都
- 第百十二回 京に伝わる恋物語
- 第百十一回 鵜飼(うかい)
- 第百十回 扇子(せんす)
- 第百九回 京の社寺と山
- 第百八回 春の京菓子
- 第百七回 幻の京都
- 第百六回 京の家紋
- 第百五回 京の門前菓子
- 第百四回 京の通り名
- 第百三回 御土居(おどい)
- 第百二回 文学に描かれた京都
- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句
- 第百回 夏の京野菜
- 第九十九回 若冲と近世日本画
- 第九十八回 京の鍾馗さん
- 第九十七回 言いまわし・ことわざ
- 第九十六回 京の仏師
- 第九十五回 鴨川
- 第九十四回 京の梅
- 第九十三回 ご朱印
- 第九十二回 京の冬の食習慣
- 第九十一回 京の庭園
- 第九十回 琳派(りんぱ)
- 第八十九回 京の麩(ふ)
- 第八十八回 妖怪紀行
- 第八十七回 夏の京菓子
- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族
- 第八十五回 新選組
- 第八十四回 京のお弁当
- 第八十三回 京都の湯
- 第八十二回 京の禅寺
- 第八十一回 京の落語
- 第八十回 義士ゆかりの地・山科
- 第七十九回 京の紅葉
- 第七十八回 京の漫画
- 第七十七回 京の井戸
- 第七十六回 京のお地蔵さん
- 第七十五回 京の名僧
- 第七十四回 京の別邸
- 第七十三回 糺(ただす)の森
- 第七十二回 京舞
- 第七十一回 香道
- 第七十回 天神さん
- 第六十九回 平安京
- 第六十八回 冬の京野菜
- 第六十七回 茶の湯(茶道)
- 第六十六回 京の女流文学
- 第六十五回 京の銭湯
- 第六十四回 京の離宮
- 第六十三回 京の町名
- 第六十二回 能・狂言
- 第六十一回 京の伝説
- 第六十回 京狩野派
- 第五十九回 京寿司
- 第五十八回 京のしきたり
- 第五十七回 百人一首
- 第五十六回 京の年末
- 第五十五回 いけばな
- 第五十四回 京の城
- 第五十三回 観月行事
- 第五十二回 京の塔
- 第五十一回 錦市場
- 第五十回 京の暖簾
- 第四十九回 大原女
- 第四十八回 京友禅
- 第四十七回 京のひな祭り
- 第四十六回 京料理
- 第四十五回 京の町家〈内観編〉
- 第四十四回 京の町家〈外観編〉
- 第四十三回 京都と映画
- 第四十二回 京の門
- 第四十一回 おばんざい
- 第四十回 京の焼きもの
- 第三十九回 京の七不思議
- 第三十八回 京の作庭家
- 第三十七回 室町文化
- 第三十六回 京都御所
- 第三十五回 京の通り
- 第三十四回 節分祭
- 第三十三回 京の七福神
- 第三十二回 京の狛犬
- 第三十一回 伏見の酒
- 第三十回 京ことば
- 第二十九回 京の文明開化
- 第二十八回 京の魔界
- 第二十七回 京の納涼床
- 第二十六回 夏越祓
- 第二十五回 葵祭
- 第二十四回 京の絵師
- 第二十三回 涅槃会
- 第二十二回 京のお漬物
- 第二十一回 京の幕末
- 第二十回 京の梵鐘
- 第十九回 京のお豆腐
- 第十八回 時代祭
- 第十七回 京の近代建築
- 第十六回 京のお盆行事
- 第十五回 京野菜
- 第十四回 京都の路地
- 第十三回 宇治茶
- 第十一回 京菓子の歴史
- 第十回 枯山水庭園の眺め方
- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド
- 第八回 顔見世を楽しむ
- 第七回 特別拝観の楽しみ方
- 第六回 京都の着物
- 第五回 仏像の見方
- 第四回 送り火の神秘
- 第三回 祇園祭の楽しみ方
- 第二回 京の名水めぐり
- 第一回 池泉庭園の眺め方