
貴族の装いには多くの決まりがあります。男性は日常では狩衣(かりぎぬ)などの簡素な服、正式な場では束帯(そくたい)を着ました。また女性は単(ひとえ)と長袴(ながばかま)の単袴姿が基本で、朝廷に出仕する際の正装は、単袴姿に袿(うちき)などを何枚も重ね約10kgにもなる女房装束(十二単)でした。
![<束帯> [冠(垂纓冠) かんむり(すいえいのかんむり)]結った髪と冠をかんざしのようなもので貫き固定しました。病気の時でさえも冠を外すことは許されませんでした。 [平緒 ひらお]飾りの太刀を吊るためのもので、腰に巻いて結び余りを前に垂らしました。 [袍 ほう]1番上に着る衣のことで、官位で色が分けられており、上級貴族は黒でした。 [ココがツウ]後ろに長く垂れる布は袍の下に着る下襲のすそで裾(きょ)と言います。官位が高いほど長くなりました](img/201401/cont1-img1.jpg)
![<女房装束> [袿 うちき]何枚も重ね着する衣で、季節感のある配色がセンスの見せどころ。十数枚重ねることもあったそうですが、平安時代末期には5枚重ねに限定されました。 [唐衣 からぎぬ]1番上に着る、高価で美しい衣。地位によって色目や文様に区別がありました。 [化粧]顔には白粉を塗り、眉は全部抜いた後に墨で線を引き、口は下唇に少しだけ紅を差しました。 [髪]髪は長いほど美人とされ、毎朝米のとぎ汁をくしにつけて髪をすいていました。 [ココがツウ]長袴は平安時代にのみ着用されたもので、板敷きが多かったこの時代、寒さをしのぐ役割があったとされます](img/201401/cont1-img2.jpg)
![[千年の都 平安京]現代の京都に息づく、王城の地・平安京。日本の都として繁栄した平安京の歴史や人々の暮らしについて、らくたびの若村亮さんが解説 します。](/navi/kyoto_tsu/img/201401/main.jpg)
794(延暦13)年、桓武天皇によって長岡京から山背国(やましろのくに)(現在の京都市)に都が遷(うつ)され、永遠に平和で安らかであるようにとの願いを込め“平安京”と名付けられました。幅85mもの朱雀大路は、道の中央で右京と左京に分けられ、朱雀大路の北端には天皇が住む内裏や儀式や政務を行う施設のある大内裏(だいだいり)を造り、南端には羅城門(らじょうもん)を設置しました。やがて、左京に人々が集中し、都の北側や東側にも市街地が形成されます。平安京は、姿を変えながら、1869(明治2)年に東京へ遷都されるまで千年以上の間、天皇や貴族が住む日本の首都として、政治・文化の中心的役割を果たしました。

平安京の全盛期には、東西約4.5km、南北約5.2kmという土地に、推定十数万もの人々が暮らしていました。貴族たちは内裏や周辺の役所で宮仕えをし、季節の移ろいや年中行事を大切にした生活を送ります。その中で、寝殿造の邸宅や雅な衣装など、日本らしい国風文化が栄え、暮らしも豊かになっていきました。
![[地図でひも解く都と四神の謎]日本の首都として一大国家を築き上げた平安京。理想的な地として風水思想によってここが選ばれた理由や、都の守護として社寺を幾重にも配置した意図を地図を交えて解説します。](/navi/kyoto_tsu/img/201401/section1-ttl.jpg)

中国で発展した風水思想に基づき、東西南北を司る神獣らに守られた「四神相応の地」に都を建設。東の青龍は水が流れる場所の鴨川、西の白虎は大きな道がある山陰道、南の朱雀は広く開けた土地の巨椋(おぐら)池、北の玄武は山や丘がある船岡山にあたるとされています。

都の周囲には災いを防ぐため、多くの王城鎮護の社寺が設けられました。北東は鬼神が出入りする鬼門とされ、比叡山に延暦寺、そのふもとに赤山禅院が置かれました。一方、北西は怨霊や災いが入る天門と呼ばれ、その守護として愛宕神社が置かれました。

平安京は左右対称が徹底された都市で、朱雀大路を挟んで東は「左京」、西は「右京」と呼ばれました。左京と右京には、それぞれ対称となる位置に東寺と西寺、東市と西市が配置されました。
唐の都の名から、左京は「洛陽」、右京は「長安」とも呼ばれました。やがて左京が都の中心となって栄えたので、都全体が洛陽と呼ばれるようになり、洛中、洛外、上洛(京都に行くこと)などの言葉が生まれました










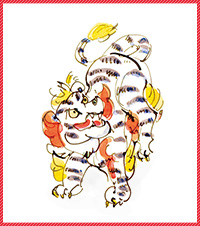
![[衣食住で知る平安貴族の暮らし]平安京に雅やかな国風文化が花開いた時代、貴族は実際にどのような生活を送っていたのでしょう。衣食住をテーマに、平安貴族の暮らしを紹介します。](/navi/kyoto_tsu/img/201401/section2-ttl.jpg)

貴族の装いには多くの決まりがあります。男性は日常では狩衣(かりぎぬ)などの簡素な服、正式な場では束帯(そくたい)を着ました。また女性は単(ひとえ)と長袴(ながばかま)の単袴姿が基本で、朝廷に出仕する際の正装は、単袴姿に袿(うちき)などを何枚も重ね約10kgにもなる女房装束(十二単)でした。
![<束帯> [冠(垂纓冠) かんむり(すいえいのかんむり)]結った髪と冠をかんざしのようなもので貫き固定しました。病気の時でさえも冠を外すことは許されませんでした。 [平緒 ひらお]飾りの太刀を吊るためのもので、腰に巻いて結び余りを前に垂らしました。 [袍 ほう]1番上に着る衣のことで、官位で色が分けられており、上級貴族は黒でした。 [ココがツウ]後ろに長く垂れる布は袍の下に着る下襲のすそで裾(きょ)と言います。官位が高いほど長くなりました](img/201401/cont1-img1.jpg)
![<女房装束> [袿 うちき]何枚も重ね着する衣で、季節感のある配色がセンスの見せどころ。十数枚重ねることもあったそうですが、平安時代末期には5枚重ねに限定されました。 [唐衣 からぎぬ]1番上に着る、高価で美しい衣。地位によって色目や文様に区別がありました。 [化粧]顔には白粉を塗り、眉は全部抜いた後に墨で線を引き、口は下唇に少しだけ紅を差しました。 [髪]髪は長いほど美人とされ、毎朝米のとぎ汁をくしにつけて髪をすいていました。 [ココがツウ]長袴は平安時代にのみ着用されたもので、板敷きが多かったこの時代、寒さをしのぐ役割があったとされます](img/201401/cont1-img2.jpg)

食事は原則10時と16時の2回。食材は、米や穀物、野菜に加え、猪や鹿の肉、魚介類の干物など種類豊富でしたが、味はほとんど付いておらず、好みで塩などの調味料を付けて食べました。1月15日に食べる小豆粥(あずきがゆ)や9月9日の重陽(ちょうよう)の節句に飲む菊酒のように、季節や儀式に関わる食習慣もありました。
![[菓子]お菓子は「くだもの」とも呼ばれ、果物や中国伝来の唐菓物(からくだもの)が代表的です。 [主食・調味料]強飯(こわめし)と呼ばれた、蒸した餅米などの周りには、調味料が置かれました。塩、酢、酒と、みその原型である醤(ひしお)の4つで、自分好みの味付けをしました。 [台盤 だいばん]食事を乗せる4脚の台で、料理を盛った器を数多く並べました。 [ココがツウ]現在、餅米に小豆などを混ぜ、蒸したごはんを「おこわ」と言いますが、これは強飯に由来します](/navi/kyoto_tsu/img/201401/cont2-img.jpg)

平安貴族の邸宅は寝殿造と呼ばれる建築様式で、一町四方(120平方メートル)の大きさが基本です。築地塀(ついじべい)で囲まれた敷地に池泉庭園と、庭を囲むように「コ」の字型に建物が配置されました。寝殿には壁がほとんどなく、これは蒸し暑い京都の夏に、池からの涼風を取り入れるための工夫でした。
![[寝殿 しんでん]主人が住む建物。基本的に壁がない大きなワンルームで床は板敷き。必要に応じて屏風やついたてなどで分割し、調度品が置かれました。これを室礼(しつらい)と呼び、センスよく整えることが重要とされました。 [釣殿 つりどの]東西の対屋から南へのびる通路でつながれた、池に面した建物。暑い日に涼んだり、魚釣りを楽しんだりする場所でした。 [対屋 たいのや]寝殿の東、西、北などに配置された建物で、家族の居住空間。寝殿とは屋根のついた通路でつながっています。 [庭園]池や滝、築山などで構成されます。寝殿の南側に広がる白砂を敷いた「南庭(だんてい)」は、儀式などで使用する大切な空間でした。](/navi/kyoto_tsu/img/201401/cont3-img.jpg)
平安京の一般庶民は、貴族の従者や商工業者などがほとんどで、激しい労働に従事する人々は1日2度の食事に加え、間食(かんじき)という昼食をとりました。職業に合わせた活動しやすい服装で、住居は間口が狭く、隣家と軒を接する長屋で暮らしていました。
![]()
![[受け継がれる年中行事や風習]平安京では、様々な儀式や年中行事が行われ、中には現代まで綿々と受け継がれているものもあります。](/navi/kyoto_tsu/img/201401/section3-ttl.jpg)


現在も正月の“鏡餅”として続く風習。
丸く平たい餅を2~3個重ねます。神様に供えるもので食べませんでした。



下鴨神社と上賀茂神社の祭礼。当時、祭りとは賀茂祭をさしました。葵祭として、今も5月15日に行われています。
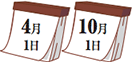




月が最も美しい日とされ、舟遊びや歌を楽しむ宴を催しました。今も「中秋の名月」として月を見る風習が残ります。


1年の最後に宮中で行われた鬼払いの儀式。
豆まきで鬼を追い払う節分の元になったとされています。