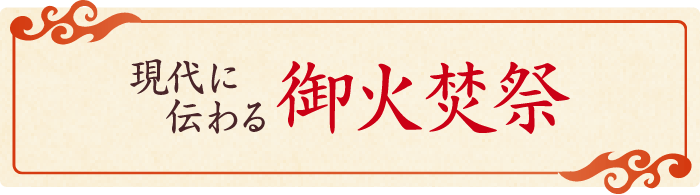京都ツウのススメ
第百六十回 御火焚祭(おひたきさい)
京の初冬の風物詩豪快に燃え上がる火に、感謝と願いを込める御火焚祭について、らくたびの谷口真由美さんがご紹介します。
基礎知識
其の一、
- 秋の収穫を神様に感謝し、無病息災などを願う行事です
其の二、
- 燃え盛る火の中に神様を見出し、その威力で御加護を授かります
其の三、
- ミカンやおこしなど御火焚祭にち なんだ食べ物があります
由来は神社によって様々
京都の各神社で11月になると行われる御火焚祭。平安時代から続く宮中行事の新嘗祭(にいなめさい)が江戸時代に民間に広まったという説や、竈(かまど)の神様に感謝するためなど由来は諸説あり、様々な信仰が融合してきました。ご祭神への感謝とご利益を願うといった意味もあります。古来より、火は生活になくてはならないもので、人間は火を使うことができる唯一の生き物。人は燃え上がる火の威力に神様の姿を見出し、神聖なものとしてきました。
昔ながらの神事を伝える
時代が進み、火の代わりにガスや電気が普及しましたが、京都には五山の送り火や愛宕詣り(あたごまいり)など、火に対する信仰が息づいています。御火焚祭もそのひとつで、火焚串(護摩木(ごまき))に願いを書き込み、焚き上げる神事が現代に継承されています。神事の後に神様のお下がりとして配られる御火焚饅頭(おひたきまんじゅう)・ミカン・おこしを食べると、1年の無病息災や火難除けなどのご利益があると言います。
京都にある多くの神社で行われ、
地元住民にとっても大切な年間行事。


昔は各町内でも行われていましたが、現在では神社と一部の寺院のみ。一般的には本殿での儀式・御火焚神事・神楽奉納の3つの神事を行います。神社によっては、釜で沸かした湯を振りかけて参拝者を清める湯立神楽を行うところもあります。ハイライトは、参拝者が願いを書いて奉納した火焚串を、焚き上げて祈願する御火焚神事です。火の力で願いを天に届け、ケガレをはらいます。

京都の人は「おひたきさん」「おしたきさん」「おしたけさん」と呼び親しんで、この神事を大切にしています
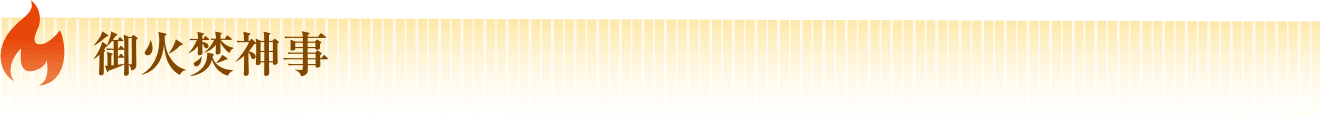
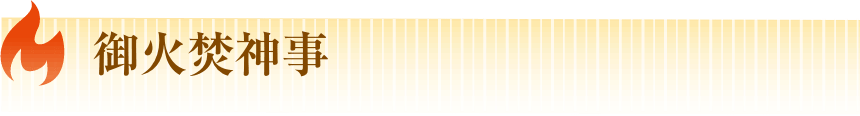
火焚串を組み上げた火床に火をつけ、祝詞を上げながら火焚串を投げ入れて焚き上げます。
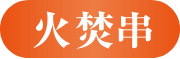
家内安全」などの願い事と名前を書きます。護摩木と呼ぶところもあります。


火焚串を積み重ねて作る火床は由来によって形が変わり、ふいご型、円柱型、井桁(いげた)などに組み上げます。使わない火床もあり、神前の灯明から火を移します。

〈花山稲荷神社〉 ふいご型
※ふいごとは、火力を強めるための送風装置

〈貴船神社〉円柱型
火焚串を円柱に組み上げます

〈伏見稲荷大社〉
杉の木を井桁に組んで檜葉を乗せます
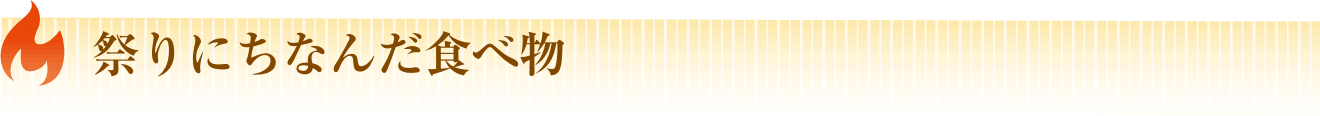


平安時代、火を焚いてミカンを供え、魑魅魍魎(ちみもうりょう)をはらった「道饗祭(みちあえのまつり)」の名残りと言われています。お下がりのミカンを食べると、1年間は風邪をひかないとされます。


火炎宝珠の焼き印が押された紅白の饅頭。火の用心と厄除け招福の願いが込められています。「おたま」とも呼びます。

御火焚饅頭は、元は餅屋が作るものでした。白には小豆のこし餡を、紅には粒餡を入れる決まりがあります

火の意味を持つ三角形で、新米で作られた米菓子です。ほんのりとした柚子の風味です。
水や火の恵みに感謝
貴船神社(きふねじんじゃ)
〔左京区〕例年11月7日
ロクロヒキリと呼ばれる古代から伝わる火をおこす道具で種火を作り、約1万本の火焚串を円柱に組み上げた護摩壇に火を点けます。

ロクロヒキリ

貴船神社では、ロクロヒキリを使う様子を公開しています
闇夜で行う神秘な神事
由岐神社(ゆきじんじゃ)
〔左京区〕例年11月8日・9日・15日 ※今年は一般参加不可
本殿のほか、境外の石寄社・岩上社・八幡宮社で計3日間、夜に行われます。柴を詰め、御幣を挿した太鼓柴と呼ばれる2基の火床を焚きます。
京都最大級のお焚き上げ
伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)
〔伏見区〕例年11月8日
本殿背後の祭場に3基の火床を設け、神田でとれた稲のワラを燃やした後、全国から寄せられた10数万本の願い事が書かれた火焚串を焚き上げます。
焼きミカンで風邪予防
花山稲荷神社(かざんいなりじんじゃ)
〔山科区〕例年11月の第2日曜 ※今年は一般参加不可
平安時代、三条小鍛冶宗近がこの地にふいごを築き、名刀「小狐丸」を作った故事にちなんだ護摩壇で、残り火で焼いたミカンを持ち帰ります。
火焚串を竈型に組み上げる
車折神社(くるまざきじんじゃ)
〔右京区〕例年11月23日
竈の守護神の奥津彦神・奥津姫を迎え、五穀豊穣を感謝。数千本の火焚串を竈型に組み上げ、四方の焚き口から火を点ける「かまど祓(はらい)」の神事を執行。

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団
- 第二百六回 京都の酒
- 第二百五回 京都の公家(くげ)
- 第二百四回 自然豊かな山里 大原
- 第二百三回 京都と七夕
- 第二百二回 幕末の京都と藩邸
- 第二百一回 京都と水
- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺
- 第百九十九回 京都画壇と美人画
- 第百九十八回 京都の山
- 第百九十七回 京都と豆腐
- 第百九十六回 南座と歌舞伎
- 第百九十五回 京都の巨木
- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)
- 第百九十三回 秋の京菓子
- 第百九十二回 京都の植物
- 第百九十一回 京都の風習
- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)
- 第百八十九回 京都と魚
- 第百八十八回 京都とお花見
- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地
- 第百八十六回 京都の地ソース
- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地
- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い
- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)
- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば
- 第百八十一回 京都の中華料理
- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都
- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子
- 第百七十八回 京都と徳川家
- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)
- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)
- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)
- 第百七十四回 京の難読地名
- 第百七十三回 京の縁日
- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)
- 第百七十一回 京都の通称寺
- 第百七十回 京都とキリスト教
- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り
- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え
- 第百六十七回 京の城下町 伏見
- 第百六十六回 京の竹
- 第百六十五回 子供の行事・儀式
- 第百六十四回 文豪と京の味
- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理
- 第百六十二回 京都のフォークソング
- 第百六十一回 京と虎、寅
- 第百六十回 御火焚祭
- 第百五十九回 鴨川の橋
- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)
- 第百五十七回 京都とスポーツ
- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見
- 第百五十五回 京都の喫茶店
- 第百五十四回 京の刃物
- 第百五十三回 京都の南蛮菓子
- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)
- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉
- 第百五十回 京のお雑煮
- 第百四十九回 京の牛肉文化
- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)
- 第百四十七回 明治の京都画壇
- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)
- 第百四十五回 ヴォーリズ建築
- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)
- 第百四十三回 京の人形
- 第百四十二回 京の社寺と動物
- 第百四十一回 鳥居(とりい)
- 第百四十回 冬の食べ物
- 第百三十九回 能・狂言と京都
- 第百三十八回 京都と様々な物の供養
- 第百三十六回 京都とビール
- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)
- 第百三十四回 精進料理
- 第百三十三回 明治時代の京の町
- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物
- 第百三十一回 京の調味料
- 第百三十回 高瀬川
- 第百二十九回 蹴鞠
- 第百二十八回 歌舞伎
- 第百二十七回 京都に残るお屋敷
- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]
- 第百二十五回 京の学校
- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり
- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>
- 第百二十二回 京都とフランス
- 第百二十一回 京の石仏
- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)
- 第百十九回 生き物由来の地名
- 第百十八回 京都の路面電車
- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納
- 第百十六回 京の歴食
- 第百十五回 曲水の宴
- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)
- 第百十三回 パンと京都
- 第百十二回 京に伝わる恋物語
- 第百十一回 鵜飼(うかい)
- 第百十回 扇子(せんす)
- 第百九回 京の社寺と山
- 第百八回 春の京菓子
- 第百七回 幻の京都
- 第百六回 京の家紋
- 第百五回 京の門前菓子
- 第百四回 京の通り名
- 第百三回 御土居(おどい)
- 第百二回 文学に描かれた京都
- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句
- 第百回 夏の京野菜
- 第九十九回 若冲と近世日本画
- 第九十八回 京の鍾馗さん
- 第九十七回 言いまわし・ことわざ
- 第九十六回 京の仏師
- 第九十五回 鴨川
- 第九十四回 京の梅
- 第九十三回 ご朱印
- 第九十二回 京の冬の食習慣
- 第九十一回 京の庭園
- 第九十回 琳派(りんぱ)
- 第八十九回 京の麩(ふ)
- 第八十八回 妖怪紀行
- 第八十七回 夏の京菓子
- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族
- 第八十五回 新選組
- 第八十四回 京のお弁当
- 第八十三回 京都の湯
- 第八十二回 京の禅寺
- 第八十一回 京の落語
- 第八十回 義士ゆかりの地・山科
- 第七十九回 京の紅葉
- 第七十八回 京の漫画
- 第七十七回 京の井戸
- 第七十六回 京のお地蔵さん
- 第七十五回 京の名僧
- 第七十四回 京の別邸
- 第七十三回 糺(ただす)の森
- 第七十二回 京舞
- 第七十一回 香道
- 第七十回 天神さん
- 第六十九回 平安京
- 第六十八回 冬の京野菜
- 第六十七回 茶の湯(茶道)
- 第六十六回 京の女流文学
- 第六十五回 京の銭湯
- 第六十四回 京の離宮
- 第六十三回 京の町名
- 第六十二回 能・狂言
- 第六十一回 京の伝説
- 第六十回 京狩野派
- 第五十九回 京寿司
- 第五十八回 京のしきたり
- 第五十七回 百人一首
- 第五十六回 京の年末
- 第五十五回 いけばな
- 第五十四回 京の城
- 第五十三回 観月行事
- 第五十二回 京の塔
- 第五十一回 錦市場
- 第五十回 京の暖簾
- 第四十九回 大原女
- 第四十八回 京友禅
- 第四十七回 京のひな祭り
- 第四十六回 京料理
- 第四十五回 京の町家〈内観編〉
- 第四十四回 京の町家〈外観編〉
- 第四十三回 京都と映画
- 第四十二回 京の門
- 第四十一回 おばんざい
- 第四十回 京の焼きもの
- 第三十九回 京の七不思議
- 第三十八回 京の作庭家
- 第三十七回 室町文化
- 第三十六回 京都御所
- 第三十五回 京の通り
- 第三十四回 節分祭
- 第三十三回 京の七福神
- 第三十二回 京の狛犬
- 第三十一回 伏見の酒
- 第三十回 京ことば
- 第二十九回 京の文明開化
- 第二十八回 京の魔界
- 第二十七回 京の納涼床
- 第二十六回 夏越祓
- 第二十五回 葵祭
- 第二十四回 京の絵師
- 第二十三回 涅槃会
- 第二十二回 京のお漬物
- 第二十一回 京の幕末
- 第二十回 京の梵鐘
- 第十九回 京のお豆腐
- 第十八回 時代祭
- 第十七回 京の近代建築
- 第十六回 京のお盆行事
- 第十五回 京野菜
- 第十四回 京都の路地
- 第十三回 宇治茶
- 第十一回 京菓子の歴史
- 第十回 枯山水庭園の眺め方
- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド
- 第八回 顔見世を楽しむ
- 第七回 特別拝観の楽しみ方
- 第六回 京都の着物
- 第五回 仏像の見方
- 第四回 送り火の神秘
- 第三回 祇園祭の楽しみ方
- 第二回 京の名水めぐり
- 第一回 池泉庭園の眺め方