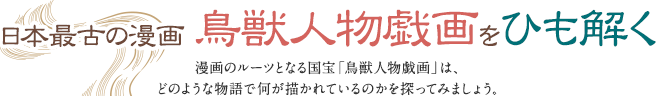京都ツウのススメ
第七十八回 京の漫画
![[京都から全国へ漫画の原点(ルーツ)] 国宝「鳥獣人物戯画」を中心に、京都発祥の漫画についてらくたびの山村純也さんが解説します。](/navi/kyoto_tsu/img/201410/main.jpg)
- 其の一、
- 平安時代、漫画のルーツと言われる絵巻物「鳥獣人物戯画(ちょうじゅうじんぶつぎが)」が誕生しました
- 其の二、
- 江戸時代の「鳥羽絵(とばえ)」など、娯楽としての絵画が後に漫画と呼ばれます
- 其の三、
- 明治時代に漫画が流行し、著名な絵師たちも漫画を描きました
漫画の成り立ち
京都・高山寺(こうさんじ)が所蔵する絵巻物「鳥獣人物戯画」は平安時代末期から鎌倉時代に描かれ、日本最古の漫画とされています。戯画とは世相を映し、戯れに描いた絵のこと。作者と言われる鳥羽僧正(とばそうじょう)の名は、江戸時代に関西から広まって流行した、日常生活を題材とする滑稽(こっけい)画の総称「鳥羽絵」としても残っています。一方「漫画」という呼称は、浮世絵師・山東京伝(さんとうきょうでん)が1798(寛政10)年発行の絵本の序文で“気の向くままに(絵を)描く”という意味で使ったのが初めとされています。その後「○○漫画」という書名の戯画集がいくつも出版されるようになり、江戸時代後期から明治時代前期にかけて全15編が発行された葛飾北斎の「北斎漫画」は大好評を博しました。
京都が発信する漫画文化
「鳥獣人物戯画」に始まる漫画文化。発祥の地・京都では現在も様々な取り組みが行われています。漫画について学べる環境が整った大学があるほか、日本初の漫画文化施設・京都国際マンガミュージアムも開設されました。「京都国際マンガ・アニメフェア」などのイベントも行われ、街全体で漫画文化を盛り上げています。
京都・高山寺に伝わる絵巻物「鳥獣人物戯画」は全4巻からなり、平安時代後期に甲・乙巻、鎌倉時代に丙・丁巻が制作されました。各巻のサイズは幅約30㎝で長さ約11mにも及びます。甲巻には擬人化された動物たちの物語性のある動き、乙巻は空想上や実在する動物の生態図、丙巻は前半に人物、後半に動物たちの遊ぶさま、丁巻は勝負事や行事などの人間社会が描かれています。セリフや解説文は全くなく、絵だけで物語を楽しめます。
![]() 作者には高僧・鳥羽僧正や絵仏師・定智(じょうち)などの名前が挙がっているものの、誰が何のために描いたのかは現在も不明です
作者には高僧・鳥羽僧正や絵仏師・定智(じょうち)などの名前が挙がっているものの、誰が何のために描いたのかは現在も不明です
甲巻では、動物たちが遊び戯れる様子が擬人化して描かれています。水遊び、相撲、射的などに興じるウサギやカエル、サルたちの躍動感あふれる動きや生き生きとした表情に注目!
![]() 絵巻物は右から左へ見ていきます。冒頭の場面から時間をさかのぼって物語る手法が取られています
絵巻物は右から左へ見ていきます。冒頭の場面から時間をさかのぼって物語る手法が取られています
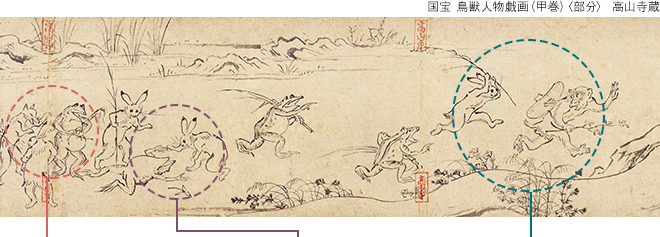
-
カエルが倒れている場所に、動物たちが集まっています。ウサギはキツネの腰に付いたオモダカの葉が気になるようですが、結末は描かれていないので、サルとキツネのどちらが犯人なのかはわかりません。
-
カエルが仰向けで気絶しています。通りかかったウサギが声をかけますが、反応がありません。また、そばに落ちているオモダカの葉は、事件と解くカギとして描かれているようです。
-
いたずら好きなサルが笑いながら逃げています。それをススキの刀をかざして追いかけるウサギとカエル。一体、何があったのでしょうか。
京都国立博物館 「国宝 鳥獣戯画と高山寺」 ●2014年10/7(火)~11/24(休・月)
江戸時代後期に活躍した浮世絵師。「北斎漫画」は1814(文化11)年に初編発表、全15編が発行されました。人物、風俗、動植物、妖怪変化など4,000点が描かれ、モネやゴッホなど印象派の画家たちにも影響を与えました。
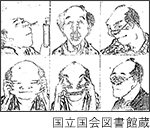
京都の呉服店に生まれ、40歳で日本画の絵師となった光琳。1817(文化14)年に、いくつもの戯画風の絵が描かれた作品集「光琳漫画」が出版されました。書名には当時流行していた「漫画」が付けられました。
![]() 現在のコミックとは違いストーリーはなく、四季の植物などを墨絵で描いた、いわゆる画集のようなものでした
現在のコミックとは違いストーリーはなく、四季の植物などを墨絵で描いた、いわゆる画集のようなものでした
幕末から明治時代にかけて活躍、最後の浮世絵師と呼ばれています。1885(明治18)年発行の「芳年漫画」に見られる動きの瞬間を切り取って描く技法には、現代の漫画に通じるものがあることから、現代漫画の先駆者とも言われています。


- 第二百七回 京都の小劇場と劇団
- 第二百六回 京都の酒
- 第二百五回 京都の公家(くげ)
- 第二百四回 自然豊かな山里 大原
- 第二百三回 京都と七夕
- 第二百二回 幕末の京都と藩邸
- 第二百一回 京都と水
- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺
- 第百九十九回 京都画壇と美人画
- 第百九十八回 京都の山
- 第百九十七回 京都と豆腐
- 第百九十六回 南座と歌舞伎
- 第百九十五回 京都の巨木
- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)
- 第百九十三回 秋の京菓子
- 第百九十二回 京都の植物
- 第百九十一回 京都の風習
- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)
- 第百八十九回 京都と魚
- 第百八十八回 京都とお花見
- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地
- 第百八十六回 京都の地ソース
- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地
- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い
- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)
- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば
- 第百八十一回 京都の中華料理
- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都
- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子
- 第百七十八回 京都と徳川家
- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)
- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)
- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)
- 第百七十四回 京の難読地名
- 第百七十三回 京の縁日
- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)
- 第百七十一回 京都の通称寺
- 第百七十回 京都とキリスト教
- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り
- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え
- 第百六十七回 京の城下町 伏見
- 第百六十六回 京の竹
- 第百六十五回 子供の行事・儀式
- 第百六十四回 文豪と京の味
- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理
- 第百六十二回 京都のフォークソング
- 第百六十一回 京と虎、寅
- 第百六十回 御火焚祭
- 第百五十九回 鴨川の橋
- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)
- 第百五十七回 京都とスポーツ
- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見
- 第百五十五回 京都の喫茶店
- 第百五十四回 京の刃物
- 第百五十三回 京都の南蛮菓子
- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)
- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉
- 第百五十回 京のお雑煮
- 第百四十九回 京の牛肉文化
- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)
- 第百四十七回 明治の京都画壇
- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)
- 第百四十五回 ヴォーリズ建築
- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)
- 第百四十三回 京の人形
- 第百四十二回 京の社寺と動物
- 第百四十一回 鳥居(とりい)
- 第百四十回 冬の食べ物
- 第百三十九回 能・狂言と京都
- 第百三十八回 京都と様々な物の供養
- 第百三十六回 京都とビール
- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)
- 第百三十四回 精進料理
- 第百三十三回 明治時代の京の町
- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物
- 第百三十一回 京の調味料
- 第百三十回 高瀬川
- 第百二十九回 蹴鞠
- 第百二十八回 歌舞伎
- 第百二十七回 京都に残るお屋敷
- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]
- 第百二十五回 京の学校
- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり
- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>
- 第百二十二回 京都とフランス
- 第百二十一回 京の石仏
- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)
- 第百十九回 生き物由来の地名
- 第百十八回 京都の路面電車
- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納
- 第百十六回 京の歴食
- 第百十五回 曲水の宴
- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)
- 第百十三回 パンと京都
- 第百十二回 京に伝わる恋物語
- 第百十一回 鵜飼(うかい)
- 第百十回 扇子(せんす)
- 第百九回 京の社寺と山
- 第百八回 春の京菓子
- 第百七回 幻の京都
- 第百六回 京の家紋
- 第百五回 京の門前菓子
- 第百四回 京の通り名
- 第百三回 御土居(おどい)
- 第百二回 文学に描かれた京都
- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句
- 第百回 夏の京野菜
- 第九十九回 若冲と近世日本画
- 第九十八回 京の鍾馗さん
- 第九十七回 言いまわし・ことわざ
- 第九十六回 京の仏師
- 第九十五回 鴨川
- 第九十四回 京の梅
- 第九十三回 ご朱印
- 第九十二回 京の冬の食習慣
- 第九十一回 京の庭園
- 第九十回 琳派(りんぱ)
- 第八十九回 京の麩(ふ)
- 第八十八回 妖怪紀行
- 第八十七回 夏の京菓子
- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族
- 第八十五回 新選組
- 第八十四回 京のお弁当
- 第八十三回 京都の湯
- 第八十二回 京の禅寺
- 第八十一回 京の落語
- 第八十回 義士ゆかりの地・山科
- 第七十九回 京の紅葉
- 第七十八回 京の漫画
- 第七十七回 京の井戸
- 第七十六回 京のお地蔵さん
- 第七十五回 京の名僧
- 第七十四回 京の別邸
- 第七十三回 糺(ただす)の森
- 第七十二回 京舞
- 第七十一回 香道
- 第七十回 天神さん
- 第六十九回 平安京
- 第六十八回 冬の京野菜
- 第六十七回 茶の湯(茶道)
- 第六十六回 京の女流文学
- 第六十五回 京の銭湯
- 第六十四回 京の離宮
- 第六十三回 京の町名
- 第六十二回 能・狂言
- 第六十一回 京の伝説
- 第六十回 京狩野派
- 第五十九回 京寿司
- 第五十八回 京のしきたり
- 第五十七回 百人一首
- 第五十六回 京の年末
- 第五十五回 いけばな
- 第五十四回 京の城
- 第五十三回 観月行事
- 第五十二回 京の塔
- 第五十一回 錦市場
- 第五十回 京の暖簾
- 第四十九回 大原女
- 第四十八回 京友禅
- 第四十七回 京のひな祭り
- 第四十六回 京料理
- 第四十五回 京の町家〈内観編〉
- 第四十四回 京の町家〈外観編〉
- 第四十三回 京都と映画
- 第四十二回 京の門
- 第四十一回 おばんざい
- 第四十回 京の焼きもの
- 第三十九回 京の七不思議
- 第三十八回 京の作庭家
- 第三十七回 室町文化
- 第三十六回 京都御所
- 第三十五回 京の通り
- 第三十四回 節分祭
- 第三十三回 京の七福神
- 第三十二回 京の狛犬
- 第三十一回 伏見の酒
- 第三十回 京ことば
- 第二十九回 京の文明開化
- 第二十八回 京の魔界
- 第二十七回 京の納涼床
- 第二十六回 夏越祓
- 第二十五回 葵祭
- 第二十四回 京の絵師
- 第二十三回 涅槃会
- 第二十二回 京のお漬物
- 第二十一回 京の幕末
- 第二十回 京の梵鐘
- 第十九回 京のお豆腐
- 第十八回 時代祭
- 第十七回 京の近代建築
- 第十六回 京のお盆行事
- 第十五回 京野菜
- 第十四回 京都の路地
- 第十三回 宇治茶
- 第十一回 京菓子の歴史
- 第十回 枯山水庭園の眺め方
- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド
- 第八回 顔見世を楽しむ
- 第七回 特別拝観の楽しみ方
- 第六回 京都の着物
- 第五回 仏像の見方
- 第四回 送り火の神秘
- 第三回 祇園祭の楽しみ方
- 第二回 京の名水めぐり
- 第一回 池泉庭園の眺め方