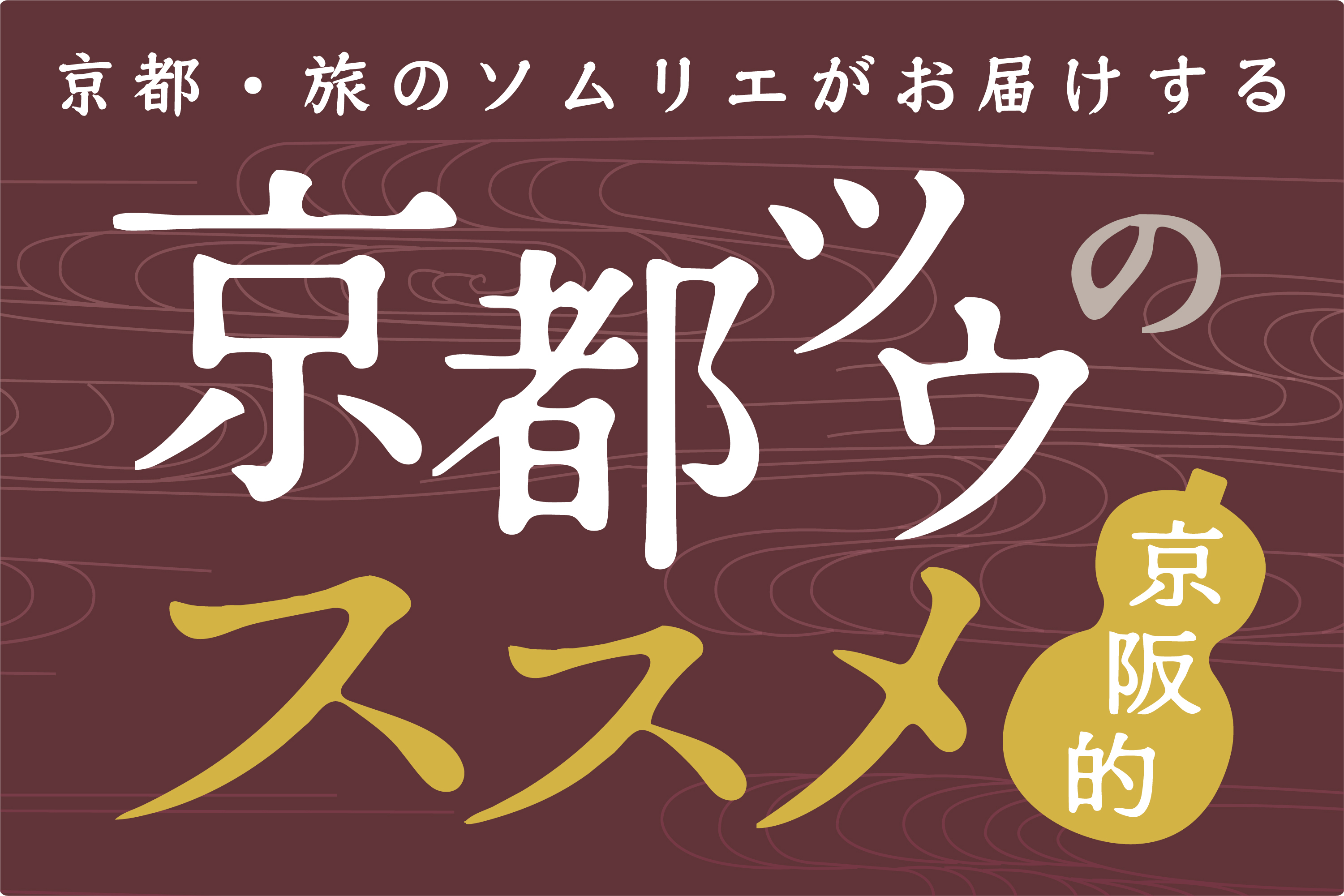
第187回
京の歌枕(うたまくら)の地
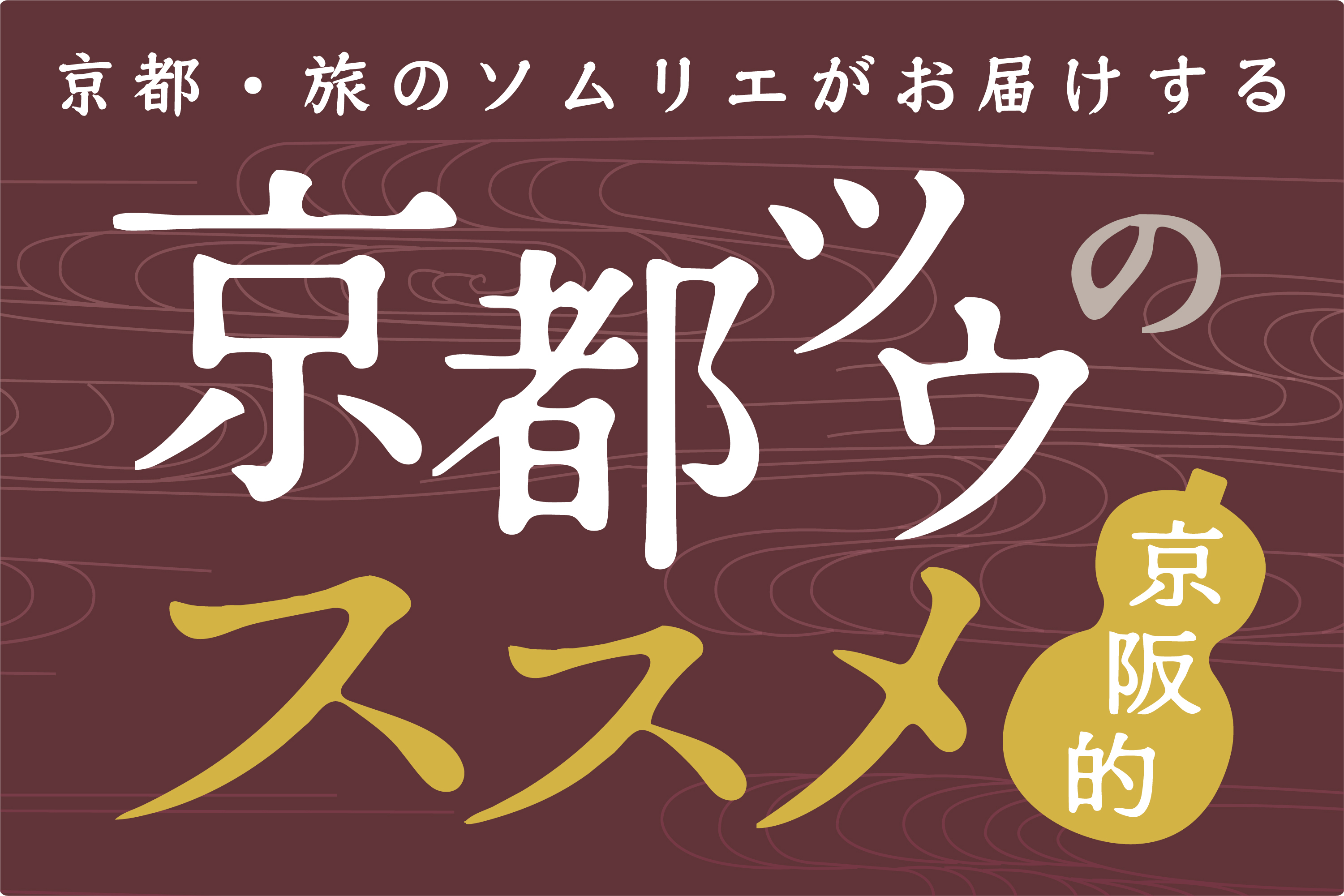
第187回
京の歌枕(うたまくら)の地

京阪的京都ツウのススメ
第187回 京の歌枕(うたまくら)の地
和歌に詠まれる京都の地名
京都にある歌枕の地を詠まれた和歌の解説とともにらくたびの田中昭美さんがご紹介します。
京の歌枕(うたまくら)の地の基礎知識
其の一、
和歌を詠むことは平安時代の貴族のたしなみのひとつでした
其の二、
歌枕とは、和歌に詠まれた古くからよく知られる名所・地名を言います
其の三、
名所旧跡が多い京都には歌枕となった地がたくさんあります
平安貴族に欠かせない和歌のたしなみ
794(延暦13)年、平安京に遷都されたことにより、京都には天皇とともに貴族が移り住みました。こうした上流階級の人々のたしなみのひとつに、和歌を詠むことが挙げられます。宮中で催された、杯を川に流し和歌を詠む曲水の宴や、神に歌を捧げて祈願する献詠祭(けんえいさい)などの神事、また日常でも挨拶や返事などで和歌を詠みました。和歌には「歌枕」と呼ばれる言葉が使われます。歌枕は和歌の題材になった地名や動植物名などと、それらを紹介した書物を指しましたが、現在では、和歌に詠まれた名所旧跡など特定の地名のことを言います。
京都には歌枕の地がいくつも
和歌には京都の地名が詠まれたものが数多くあります。平安時代以前から紅葉の名所だった「嵐山」や歴史の舞台になった「宇治」などの地名は、小倉百人一首や後拾遺(ごしゅうい)和歌集の和歌の中にも見られます。現在、下鴨神社の糺(ただす)の森を流れる「瀬見(せみ)の小川」や花街の「祇園」も歌枕として詠まれ、和歌の情景を表現する役割を担います。
京の「歌枕の地」と和歌
歌枕の地は、和歌が詠まれた時にはすでに名所などとしてよく知られていた場所でした。
京都の歌枕の地と、その歌枕を詠み込んだ和歌をひも解きます。
嵐山

大井川ふるき流れをたづねきて 嵐の山のもみぢをぞ見る/後拾遺和歌集
ともに聖帝として尊敬された宇多法皇と醍醐天皇が行幸(ぎょうこう)した大井川[大堰川]の由緒ある流れを白河上皇が訪ねた時、嵐山の紅葉が舞い散る様子を見て感激した、という心情を詠んだ歌です。
詠み人白河上皇(しらかわじょうこう)/1053~1129年
平安時代後期、約40年の長期にわたり院政を行いました。藤原氏による摂関政治が終わり、院政時代の始まりを象徴する上皇です。
歌枕としての嵐山
嵐山は天皇や貴族の遊興の地でした。紅葉の名所である「嵐山」や「小倉山」、清らかで美しい「大井川」、優美な姿の「渡月橋」はいずれも歌枕とされています。
嵐山の北西にある「愛宕(あたご)山」は信仰の山、「化野(あだしの)」は風葬の土地と知られていて、平安時代には歌枕の地になっていました
宇治

朝ぼらけ 宇治の川霧たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代(あじろ)木/小倉百人一首
宇治川の朝霧が薄らいできて、川の浅瀬に仕掛けた鮎の稚魚を獲るための杭・網代木が見えてきた景色を表現しています。網代木は平安時代、秋から冬にかけての宇治の風物詩でした。
詠み人権中納言定頼(ごんちゅうなごんさだより)/995~1045年
藤原定頼は、平安時代中期の公卿で歌人。中古三十六歌仙のひとりであり、藤原公任(きんとう)の長男です。
歌枕としての宇治
応神天皇の皇子だった菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)の離宮があったとされ、藤原道長ら貴族の別荘地でもありました。「宇治川」「宇治橋」も歌枕です。
「宇治橋」は日本三古橋に挙げられるほど古い橋で、源氏物語の宇治十帖の『浮舟』でも歌枕として和歌に詠まれています
瀬見の小川

石川や瀬見の小川の清ければ 月も流れを尋ねてぞ澄む/新古今和歌集
瀬見の小川が清らかなので、月も流れを探し求めて澄んだ水に浮かんでいる、と詠んでいます。今の「瀬見の小川」は下鴨神社[賀茂御祖神社]の糺の森の川を言いますが、当時は賀茂川を指したという説も。
詠み人鴨 長明(かものちょうめい)/1155~1216年
下鴨神社の禰宜(ねぎ)鴨長継の次男として生まれた、鎌倉時代初期の歌人。随筆『方丈記』や『無明抄(むみょうしょう)』の作者と知られます。
歌枕としての瀬見の小川
この歌は、歌合(うたあわせ)という貴族の間で流行した、和歌を1首ずつ作って優劣を競う催しで詠まれました。「瀬見の小川」という川は無いとして負けとされた長明が、判者に「瀬見の小川は賀茂神社の縁起による、賀茂川の異名」と主張し、判定が覆ったと言われています。
ここも歌枕の地
歌の題材や舞台に取り上げられる歌枕の地は、現代でも名所と言われ大勢の人が訪れる場所になっています。
祇園
かにかくに 祇園はこひし寝るときも 枕の下を水のながるる/歌集『酒ほがひ』
詠み人吉井 勇(よしい いさむ)/1886~1960年
祇園をこよなく愛した歌人・吉井勇が23歳の時に詠んだ歌。吉井が初めて出版した歌集『酒ほがひ』に掲載されています。

祇園白川にあるこの歌の碑は、吉井勇の古希を祝して京舞井上流四世家元・井上八千代、作家・谷崎潤一郎、画家・堂本印象などの友人らが建てました
大原
日数ふる 雪げにまさる炭竈(すみがま)の 煙もさびし大原の里/新古今和歌集
詠み人式子内親王(しょくしないしんのう)/1149~1201年
新三十六歌仙に選ばれた歌人の歌です。大原は「炭窯の里」と知られ、貴族などがひっそりと暮らした地でもありました。

ナビゲーターらくたび 田中 昭美さん
らくたびは、京都ツアーの企画を行うほか、京都学講座や京都本の執筆など、多彩な京都の魅力を発信しています。
制作:2024年03月




