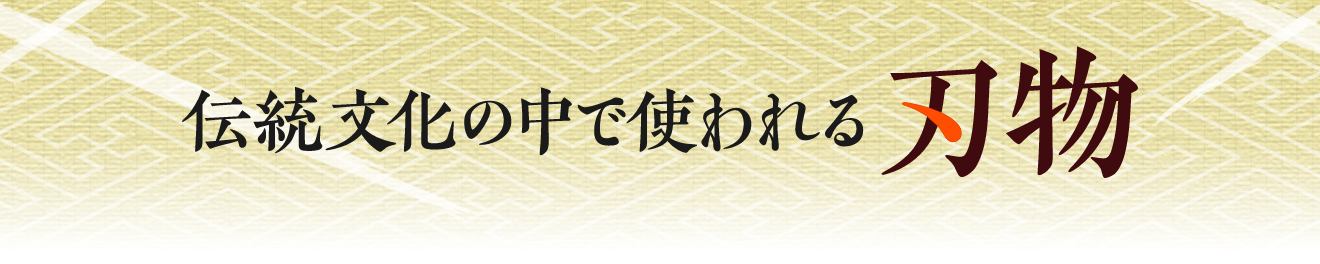京都ツウのススメ
第百五十四回 京の刃物
京文化を支えてきた刃物京都には古くから伝わる様々な文化があります。それらを支えてきた刃物やその役割についてらくたびの若村亮さんが解説します。
基礎知識
-
其の一、
- 刃物には武器である刀剣をはじめ道具としての包丁・鎌などがあります
-
其の二、
- 京都の文化や伝統産業の中では様々な刃物が使われています
-
其の三、
- 京都には鍛冶職人ゆかりの町名も残されています
武器や道具として作られた刃物
刃物には、武器である刀剣をはじめ、包丁、鉋、鎌のように何かを切ったり削ったりするための道具があります。その歴史は旧石器時代の石器に始まり、やがて青銅製や鉄製のものが誕生。日本では弥生時代後期から古墳時代にかけて鉄製の武器や道具が作られるようになったと言われます。平安京遷都の際には鍛冶の技術を持つ職人が都へ集まりました。また平安京には、太刀や金属の加工品を販売する官営市場がありました。
刀工や鍛冶職人ゆかりの地も残る
京都は、出雲地方(現・島根県)の砂鉄や玉鋼(たまはがね)、鳴滝(右京区)の砥石など、刃物造りに必要な原材料が集まりやすいこともあり、室町時代中期頃からは鍛冶の町としても栄えました。京都市内には鍛冶職人が集まっていたと思われる「鍛冶屋町」「鍛冶町」という町名が残るほか、平安時代の刀工・三条小鍛冶宗近ゆかりの地もあります。また現在も、京料理や華道といった伝統的な文化の中で専門性の高い刃物が大きな役割を果たしています。
京料理の食材を切る包丁や、いけばなのための花鋏など、
いろいろな場面で使われる刃物をご紹介します。

切れ味の良さが、食材の味わいや舌触りに影響すると言われる包丁。和食では刺身包丁や出刃包丁など、用途に合わせて包丁が使い分けられます。京都の夏の味覚であるハモ料理には鱧切り包丁と言われる骨切包丁が使われます。ずっしりとした重みを利用し、皮1枚を残しながら、硬い骨を細かく切り食べやすく調理します。


包丁と箸だけを使い、手を触れることなく魚をさばいて盛り付ける儀式を「庖丁式」と言います。吉田神社(左京区)の境内には、吉祥を表すこの儀式の創始者と言われる平安時代の貴族・藤原山蔭(やまかげ)をまつる山蔭神社があります

華道としてのいけばなは、室町時代に京都・六角堂の住職を務めていた池坊専慶(せんけい)、専応(せんのう)によって成立しました。日本最古の流派である池坊のいけばなに使われるのは池坊鋏。ハサミの形は、奈良県の正倉院に残されている金銅剪子(こんどうせんし)というハサミが元になったと言われます。持ち手の端に蕨のような曲線があり蕨手(わらびて)とも言われます。

写真:華道家元池坊総務所

聖護院かぶを使った、京都の冬の漬物が千枚漬。「千枚」と言われるほど薄く切る作業を「かんながけ」と言います。直径約15cmの大きな聖護院かぶを薄切りにするために使われるのは鉋。幅約30cm、長さ約70cmの木製の台に刃がついたもので、これを使い1枚約2〜2.5mmにスライスされます。

写真:京つけもの 西利

香道の基本である「聞香(もんこう)」は、“香木”と言われる樹木そのものの香りを楽しむもの。室町時代に八代将軍足利義政の下でその様式の基礎が整えられました。聞香に使用する一辺3~5mmほどの香木を截(き)り出す際に使われるのが香割道具。小ぶりながらも精巧な鋸(のこぎり)や鑿(のみ)などが用いられます。

写真:山田松香木店

室町時代に植林が始まったと言われる北山杉は、桂離宮や修学院離宮にも使われている銘木です。まっすぐで表面にフシの無い木肌の丸太にするための手入れに使われるのが、枝打ち鎌です。3年に1度、職人が枝に登り刃先の短い専用の枝打ち鎌を使って、枝を打ち落とします。

写真:京都北山丸太
生産協同組合
刃物に欠かせない砥石(といし)
刃物の切れ味を保つために必要なのが「研(と)ぎ」。右京区で採掘される岩石は適度な硬さや吸水性があり、仕上げ用の砥石として最高級の「鳴滝砥石」として知られていました。また「鳴滝砥石」は日本地質学会により、京都府の都道府県の石にも選ばれています。


福王子神社(右京区)では、かつて拝殿に鳴滝砥石を使った扁額(へんがく)が掲げられていました。幅約140cm、高さ約50cm、重さは約150kgで、日本で最大の砥石とも言われます
※見学は要事前予約
平安時代の刀工・三条小鍛冶宗近(むねちか)
一条天皇の命で打った名刀
日本で反りのある刀が作られ始めたのは平安時代中期。京都では刀工・三条小鍛冶宗近が活躍していました。一条天皇から名刀を作るよう命ぜられた宗近を、稲荷神社の使いの狐が手伝い、名刀「小狐丸(こぎつねまる)」が完成したという伝説があります。
宗近の邸宅があった粟田口(あわたぐち)鍛冶(かじ)町
東山区には、三条小鍛冶宗近をはじめ刀鍛冶が住んだと考えられる粟田口鍛冶町という町名があります。その周辺には、粟田神社の末社で宗近らをまつる鍛冶神社や、宗近が用いたとされる井戸「小鍛冶の井」が三門前に残る知恩院があります。

鍛冶神社

祇園祭の「長刀鉾(なぎなたほこ)」は、鉾先に大長刀を付けていることがその名の由来です。かつて大長刀には、三条小鍛冶宗近作の刀が使われていたと言われています

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団
- 第二百六回 京都の酒
- 第二百五回 京都の公家(くげ)
- 第二百四回 自然豊かな山里 大原
- 第二百三回 京都と七夕
- 第二百二回 幕末の京都と藩邸
- 第二百一回 京都と水
- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺
- 第百九十九回 京都画壇と美人画
- 第百九十八回 京都の山
- 第百九十七回 京都と豆腐
- 第百九十六回 南座と歌舞伎
- 第百九十五回 京都の巨木
- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)
- 第百九十三回 秋の京菓子
- 第百九十二回 京都の植物
- 第百九十一回 京都の風習
- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)
- 第百八十九回 京都と魚
- 第百八十八回 京都とお花見
- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地
- 第百八十六回 京都の地ソース
- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地
- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い
- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)
- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば
- 第百八十一回 京都の中華料理
- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都
- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子
- 第百七十八回 京都と徳川家
- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)
- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)
- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)
- 第百七十四回 京の難読地名
- 第百七十三回 京の縁日
- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)
- 第百七十一回 京都の通称寺
- 第百七十回 京都とキリスト教
- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り
- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え
- 第百六十七回 京の城下町 伏見
- 第百六十六回 京の竹
- 第百六十五回 子供の行事・儀式
- 第百六十四回 文豪と京の味
- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理
- 第百六十二回 京都のフォークソング
- 第百六十一回 京と虎、寅
- 第百六十回 御火焚祭
- 第百五十九回 鴨川の橋
- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)
- 第百五十七回 京都とスポーツ
- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見
- 第百五十五回 京都の喫茶店
- 第百五十四回 京の刃物
- 第百五十三回 京都の南蛮菓子
- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)
- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉
- 第百五十回 京のお雑煮
- 第百四十九回 京の牛肉文化
- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)
- 第百四十七回 明治の京都画壇
- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)
- 第百四十五回 ヴォーリズ建築
- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)
- 第百四十三回 京の人形
- 第百四十二回 京の社寺と動物
- 第百四十一回 鳥居(とりい)
- 第百四十回 冬の食べ物
- 第百三十九回 能・狂言と京都
- 第百三十八回 京都と様々な物の供養
- 第百三十六回 京都とビール
- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)
- 第百三十四回 精進料理
- 第百三十三回 明治時代の京の町
- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物
- 第百三十一回 京の調味料
- 第百三十回 高瀬川
- 第百二十九回 蹴鞠
- 第百二十八回 歌舞伎
- 第百二十七回 京都に残るお屋敷
- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]
- 第百二十五回 京の学校
- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり
- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>
- 第百二十二回 京都とフランス
- 第百二十一回 京の石仏
- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)
- 第百十九回 生き物由来の地名
- 第百十八回 京都の路面電車
- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納
- 第百十六回 京の歴食
- 第百十五回 曲水の宴
- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)
- 第百十三回 パンと京都
- 第百十二回 京に伝わる恋物語
- 第百十一回 鵜飼(うかい)
- 第百十回 扇子(せんす)
- 第百九回 京の社寺と山
- 第百八回 春の京菓子
- 第百七回 幻の京都
- 第百六回 京の家紋
- 第百五回 京の門前菓子
- 第百四回 京の通り名
- 第百三回 御土居(おどい)
- 第百二回 文学に描かれた京都
- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句
- 第百回 夏の京野菜
- 第九十九回 若冲と近世日本画
- 第九十八回 京の鍾馗さん
- 第九十七回 言いまわし・ことわざ
- 第九十六回 京の仏師
- 第九十五回 鴨川
- 第九十四回 京の梅
- 第九十三回 ご朱印
- 第九十二回 京の冬の食習慣
- 第九十一回 京の庭園
- 第九十回 琳派(りんぱ)
- 第八十九回 京の麩(ふ)
- 第八十八回 妖怪紀行
- 第八十七回 夏の京菓子
- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族
- 第八十五回 新選組
- 第八十四回 京のお弁当
- 第八十三回 京都の湯
- 第八十二回 京の禅寺
- 第八十一回 京の落語
- 第八十回 義士ゆかりの地・山科
- 第七十九回 京の紅葉
- 第七十八回 京の漫画
- 第七十七回 京の井戸
- 第七十六回 京のお地蔵さん
- 第七十五回 京の名僧
- 第七十四回 京の別邸
- 第七十三回 糺(ただす)の森
- 第七十二回 京舞
- 第七十一回 香道
- 第七十回 天神さん
- 第六十九回 平安京
- 第六十八回 冬の京野菜
- 第六十七回 茶の湯(茶道)
- 第六十六回 京の女流文学
- 第六十五回 京の銭湯
- 第六十四回 京の離宮
- 第六十三回 京の町名
- 第六十二回 能・狂言
- 第六十一回 京の伝説
- 第六十回 京狩野派
- 第五十九回 京寿司
- 第五十八回 京のしきたり
- 第五十七回 百人一首
- 第五十六回 京の年末
- 第五十五回 いけばな
- 第五十四回 京の城
- 第五十三回 観月行事
- 第五十二回 京の塔
- 第五十一回 錦市場
- 第五十回 京の暖簾
- 第四十九回 大原女
- 第四十八回 京友禅
- 第四十七回 京のひな祭り
- 第四十六回 京料理
- 第四十五回 京の町家〈内観編〉
- 第四十四回 京の町家〈外観編〉
- 第四十三回 京都と映画
- 第四十二回 京の門
- 第四十一回 おばんざい
- 第四十回 京の焼きもの
- 第三十九回 京の七不思議
- 第三十八回 京の作庭家
- 第三十七回 室町文化
- 第三十六回 京都御所
- 第三十五回 京の通り
- 第三十四回 節分祭
- 第三十三回 京の七福神
- 第三十二回 京の狛犬
- 第三十一回 伏見の酒
- 第三十回 京ことば
- 第二十九回 京の文明開化
- 第二十八回 京の魔界
- 第二十七回 京の納涼床
- 第二十六回 夏越祓
- 第二十五回 葵祭
- 第二十四回 京の絵師
- 第二十三回 涅槃会
- 第二十二回 京のお漬物
- 第二十一回 京の幕末
- 第二十回 京の梵鐘
- 第十九回 京のお豆腐
- 第十八回 時代祭
- 第十七回 京の近代建築
- 第十六回 京のお盆行事
- 第十五回 京野菜
- 第十四回 京都の路地
- 第十三回 宇治茶
- 第十一回 京菓子の歴史
- 第十回 枯山水庭園の眺め方
- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド
- 第八回 顔見世を楽しむ
- 第七回 特別拝観の楽しみ方
- 第六回 京都の着物
- 第五回 仏像の見方
- 第四回 送り火の神秘
- 第三回 祇園祭の楽しみ方
- 第二回 京の名水めぐり
- 第一回 池泉庭園の眺め方