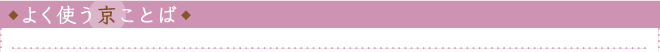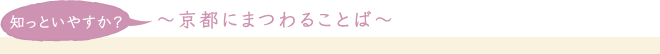京都ツウのススメ
第三十回 京ことば
![[歴史と風土に育まれた雅な京ことば] おいでやす、はんなり、おおきに・・・京都で古くから使われてきた京ことばには独特の言い回しやイントネーションがあります。今に伝わる京ことばについてらくたびの佐藤里菜子さんがご案内します。](/navi/kyoto_tsu/img/201010/main.jpg)
- 其の一、
- 京ことばは、宮中で用いた「御所(ごしょ)ことば」と商家などで用いた「町方(まちかた)ことば」から成り立っています
- 其の二、
- 独特の発音・アクセントがあり、敬語や遠回しな表現を多用するのが特徴です
- 其の三、
- 京ことばには、都で育まれた文化や暮らしの知恵が息づいています
語り継がれる京ことば
上品で柔らかな口調が耳にやさしい京ことばは、1200余年の歴史に培われた文化です。京ことばの源流は大きく「御所ことば」と「町方ことば」に分かれ、宮中で用いられた御所ことばは、明治維新まで京都御所で話されていました。町方ことばは戦前の旧京都市を中心に話されたことばで、用いる人の職業や居住地によって細かく分類されます。これらが融合して今日の京ことばを形成しています。
京ことばの特徴
京ことばは日本語のなかでも独特の響きを持つと言われています。「てぇ(手)」「めぇ(目)」のように母音を長く発音したり、「ろぉーじ(路地)」「こぉーて(買うて=買って)」などのように頭の音を長く引くため、優雅で穏やかな印象を与えます。また直接的な物言いを避け、遠回しに言う傾向が見られるのも特徴です。こうした京ことばの背景には、長い歴史の中で幾度も権力者の交代を経験した先人たちの、「本音と建前」を使い分ける暮らしの知恵が息づいていると言われています。
室町時代初期から御所に仕えた女官が使い始めたことから「女房ことば」とも言われます。主に衣食住に 関する事柄に用いることが多く、言葉遣いを丁寧にするため頭に「お」を付けたり、語尾に「もじ」などを付けて婉曲的に表現するのが特徴です。
![]()

- 「餅(もち)」の意。「お」+餅を意味する古語「搗飯(かちいい)」がなまった「かちん」

- 「会う」の意。「お目にかかる」の「おめ」+「もじ」
 身分の高い女性が入寺した尼門跡の大聖寺(京都市上京区)や霊鑑寺(京都市左京区)にはこうした御所ことばが受け継がれています
身分の高い女性が入寺した尼門跡の大聖寺(京都市上京区)や霊鑑寺(京都市左京区)にはこうした御所ことばが受け継がれています
主に中京ことば・職人ことば・花街ことばなどから成り立っています。
![]()

- 地味ではあるが上品の意。質素で堅実なことを表す公道(こうとう)が語源とも

- 「とにかく・ぎりぎり」の意の「かにかく」が語源。「かにここ間に合った」などと言う時に使う
 このほかにも京焼・京友禅などの現場で話される“伝統工芸語”や大原などの農村で話される“農業ことば”があります
このほかにも京焼・京友禅などの現場で話される“伝統工芸語”や大原などの農村で話される“農業ことば”があります
![]()
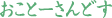
- 「事多い」の意から花街では事始めの日(12月13日)に芸妓・舞妓があいさつとして使う

- 芸妓・舞妓を送り出す時に所属する置屋(おきや)の女将さんが言うことば。座敷から早く帰られては商売に差し障るため、一般によく言う「おはようおかえりやす(早く帰ってきなさい)」ではなく、「おきばりやす(精出してがんばって)」もしくは「いっといなはい(行ってらっしゃい)」と言いました
 花街では仕事がなく暇なことを「お茶をひく」と言ったことから、「お茶」の語を避けて「ぶぶ」や「おぶー」などと言い、お茶漬けを「ぶぶ漬け」「おぶ漬け」と呼びました
花街では仕事がなく暇なことを「お茶をひく」と言ったことから、「お茶」の語を避けて「ぶぶ」や「おぶー」などと言い、お茶漬けを「ぶぶ漬け」「おぶ漬け」と呼びました
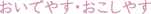
- 客を迎える時に言い、花街では「おいでやす」は初めての客に、「おこしやす」は常連に対して使うことが多い。一般には「おこしやす」の方が丁寧な言い方とされている

- 何かを終えてほっとする、気分的に疲れた時に使う

- 食べ物の食感を表し、穏やかな口当たりを指す。また落ち着きのあることを言う場合もある

- 「華あり」を語源とし、主に色合いに対して使う。上品で明るく、晴れやかな様子を言う

- 感謝の意を表すことばで、「大きに(大変、大いに)有り難し」が語源

- 耐え忍ぶ「堪忍」から、「ごめん・許してください」の意で使う

- 恐れ慎むという意の「憚(はばか)る」から、「ご苦労さん・ありがとう」の意
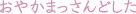
- やかましいという意の「お喧(やかま)し様」+「~どした」で、「お邪魔しました」の意
![]()
「ぶぶ漬け」とはお茶漬けの意。客に対して「まあ、ぶぶ漬けでも...」と勧めるのは遠回しに帰宅を促す儀礼的表現。言われた客は真に受けずに「いや、この辺で失礼します」と帰るのが礼儀とされます。

![]()
財産をなくすほど衣服にお金をかける京都人気質を表したことば。対して飲食にお金をかける大阪人は「食い倒れ」。また、京の人はよく気を遣うので「気倒れ」とも言われます。

取材協力/京ことばの会 参考文献/「京ことば辞典」(井之口有一・堀井令以知編)、「折々の京ことば」(堀井令以知著)ほか

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団
- 第二百六回 京都の酒
- 第二百五回 京都の公家(くげ)
- 第二百四回 自然豊かな山里 大原
- 第二百三回 京都と七夕
- 第二百二回 幕末の京都と藩邸
- 第二百一回 京都と水
- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺
- 第百九十九回 京都画壇と美人画
- 第百九十八回 京都の山
- 第百九十七回 京都と豆腐
- 第百九十六回 南座と歌舞伎
- 第百九十五回 京都の巨木
- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)
- 第百九十三回 秋の京菓子
- 第百九十二回 京都の植物
- 第百九十一回 京都の風習
- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)
- 第百八十九回 京都と魚
- 第百八十八回 京都とお花見
- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地
- 第百八十六回 京都の地ソース
- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地
- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い
- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)
- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば
- 第百八十一回 京都の中華料理
- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都
- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子
- 第百七十八回 京都と徳川家
- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)
- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)
- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)
- 第百七十四回 京の難読地名
- 第百七十三回 京の縁日
- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)
- 第百七十一回 京都の通称寺
- 第百七十回 京都とキリスト教
- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り
- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え
- 第百六十七回 京の城下町 伏見
- 第百六十六回 京の竹
- 第百六十五回 子供の行事・儀式
- 第百六十四回 文豪と京の味
- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理
- 第百六十二回 京都のフォークソング
- 第百六十一回 京と虎、寅
- 第百六十回 御火焚祭
- 第百五十九回 鴨川の橋
- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)
- 第百五十七回 京都とスポーツ
- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見
- 第百五十五回 京都の喫茶店
- 第百五十四回 京の刃物
- 第百五十三回 京都の南蛮菓子
- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)
- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉
- 第百五十回 京のお雑煮
- 第百四十九回 京の牛肉文化
- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)
- 第百四十七回 明治の京都画壇
- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)
- 第百四十五回 ヴォーリズ建築
- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)
- 第百四十三回 京の人形
- 第百四十二回 京の社寺と動物
- 第百四十一回 鳥居(とりい)
- 第百四十回 冬の食べ物
- 第百三十九回 能・狂言と京都
- 第百三十八回 京都と様々な物の供養
- 第百三十六回 京都とビール
- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)
- 第百三十四回 精進料理
- 第百三十三回 明治時代の京の町
- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物
- 第百三十一回 京の調味料
- 第百三十回 高瀬川
- 第百二十九回 蹴鞠
- 第百二十八回 歌舞伎
- 第百二十七回 京都に残るお屋敷
- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]
- 第百二十五回 京の学校
- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり
- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>
- 第百二十二回 京都とフランス
- 第百二十一回 京の石仏
- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)
- 第百十九回 生き物由来の地名
- 第百十八回 京都の路面電車
- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納
- 第百十六回 京の歴食
- 第百十五回 曲水の宴
- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)
- 第百十三回 パンと京都
- 第百十二回 京に伝わる恋物語
- 第百十一回 鵜飼(うかい)
- 第百十回 扇子(せんす)
- 第百九回 京の社寺と山
- 第百八回 春の京菓子
- 第百七回 幻の京都
- 第百六回 京の家紋
- 第百五回 京の門前菓子
- 第百四回 京の通り名
- 第百三回 御土居(おどい)
- 第百二回 文学に描かれた京都
- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句
- 第百回 夏の京野菜
- 第九十九回 若冲と近世日本画
- 第九十八回 京の鍾馗さん
- 第九十七回 言いまわし・ことわざ
- 第九十六回 京の仏師
- 第九十五回 鴨川
- 第九十四回 京の梅
- 第九十三回 ご朱印
- 第九十二回 京の冬の食習慣
- 第九十一回 京の庭園
- 第九十回 琳派(りんぱ)
- 第八十九回 京の麩(ふ)
- 第八十八回 妖怪紀行
- 第八十七回 夏の京菓子
- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族
- 第八十五回 新選組
- 第八十四回 京のお弁当
- 第八十三回 京都の湯
- 第八十二回 京の禅寺
- 第八十一回 京の落語
- 第八十回 義士ゆかりの地・山科
- 第七十九回 京の紅葉
- 第七十八回 京の漫画
- 第七十七回 京の井戸
- 第七十六回 京のお地蔵さん
- 第七十五回 京の名僧
- 第七十四回 京の別邸
- 第七十三回 糺(ただす)の森
- 第七十二回 京舞
- 第七十一回 香道
- 第七十回 天神さん
- 第六十九回 平安京
- 第六十八回 冬の京野菜
- 第六十七回 茶の湯(茶道)
- 第六十六回 京の女流文学
- 第六十五回 京の銭湯
- 第六十四回 京の離宮
- 第六十三回 京の町名
- 第六十二回 能・狂言
- 第六十一回 京の伝説
- 第六十回 京狩野派
- 第五十九回 京寿司
- 第五十八回 京のしきたり
- 第五十七回 百人一首
- 第五十六回 京の年末
- 第五十五回 いけばな
- 第五十四回 京の城
- 第五十三回 観月行事
- 第五十二回 京の塔
- 第五十一回 錦市場
- 第五十回 京の暖簾
- 第四十九回 大原女
- 第四十八回 京友禅
- 第四十七回 京のひな祭り
- 第四十六回 京料理
- 第四十五回 京の町家〈内観編〉
- 第四十四回 京の町家〈外観編〉
- 第四十三回 京都と映画
- 第四十二回 京の門
- 第四十一回 おばんざい
- 第四十回 京の焼きもの
- 第三十九回 京の七不思議
- 第三十八回 京の作庭家
- 第三十七回 室町文化
- 第三十六回 京都御所
- 第三十五回 京の通り
- 第三十四回 節分祭
- 第三十三回 京の七福神
- 第三十二回 京の狛犬
- 第三十一回 伏見の酒
- 第三十回 京ことば
- 第二十九回 京の文明開化
- 第二十八回 京の魔界
- 第二十七回 京の納涼床
- 第二十六回 夏越祓
- 第二十五回 葵祭
- 第二十四回 京の絵師
- 第二十三回 涅槃会
- 第二十二回 京のお漬物
- 第二十一回 京の幕末
- 第二十回 京の梵鐘
- 第十九回 京のお豆腐
- 第十八回 時代祭
- 第十七回 京の近代建築
- 第十六回 京のお盆行事
- 第十五回 京野菜
- 第十四回 京都の路地
- 第十三回 宇治茶
- 第十一回 京菓子の歴史
- 第十回 枯山水庭園の眺め方
- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド
- 第八回 顔見世を楽しむ
- 第七回 特別拝観の楽しみ方
- 第六回 京都の着物
- 第五回 仏像の見方
- 第四回 送り火の神秘
- 第三回 祇園祭の楽しみ方
- 第二回 京の名水めぐり
- 第一回 池泉庭園の眺め方
![[京ことばの成り立ち] 雅で美しいと言われる京ことば。その多様な表現や独特のニュアンスを生み出した京ことばの成り立ちと代表的な語句をご紹介します。](/navi/kyoto_tsu/img/201010/intro.gif)