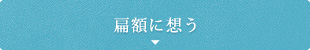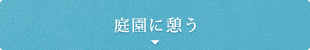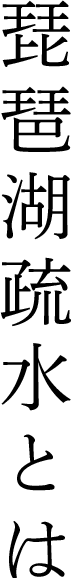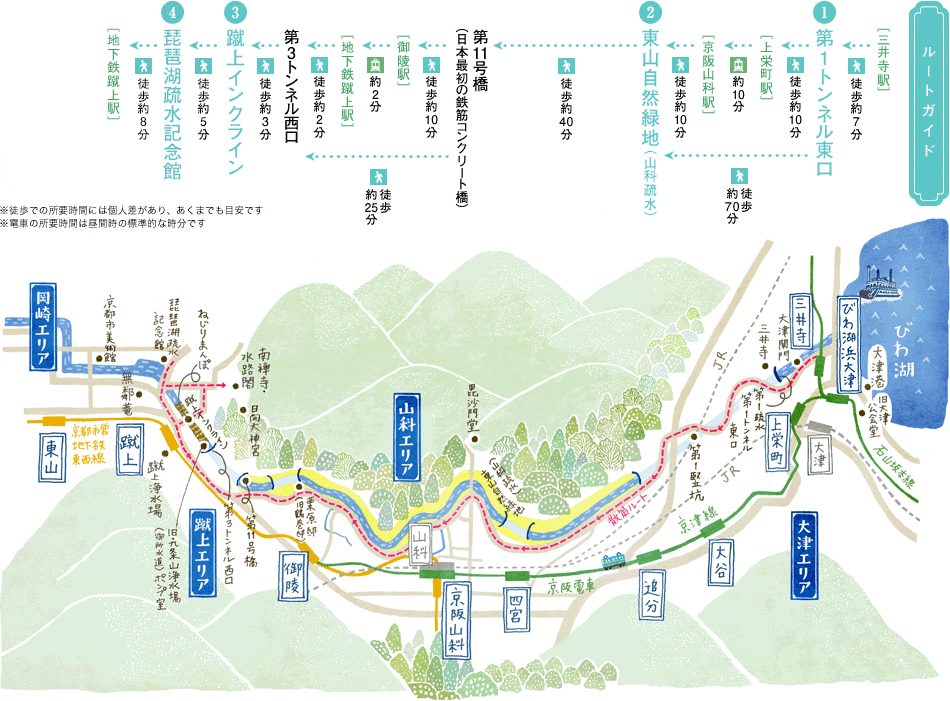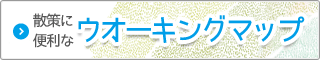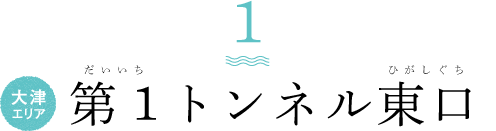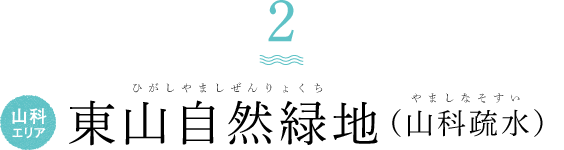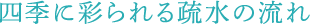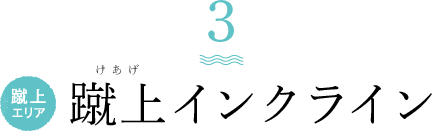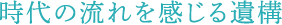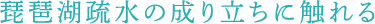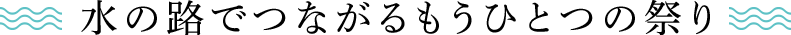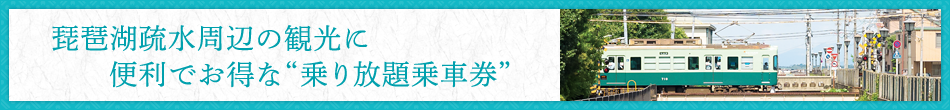路案内1 琵琶湖疏水を感じる 京都の近代化の象徴とも言える琵琶湖疏水。そのはじまり・びわ湖から、この面影を追いかけます。
琵琶湖疏水の着工は1885(明治18)年。当時の土木建設の常識を大きく超え、なんと京都府の年間予算の約2倍という巨額の費用と約5年という歳月を費やし、さらに最新の技術を投入して造られました。このプロジェクトの背景には、明治維新と東京への事実上の首都移転によって、活気をなくした京都を再び繁栄させるという大きな目的がありました。完成をみた琵琶湖疏水は、水運に加え、上水道、灌漑、そして日本初の事業用水力発電などに活用され、京都の近代化に大きく貢献したのです。
疏水が流れるのは、びわ湖畔の三保ヶ崎から伏見・濠川までの約20㎞。その起点となる大津、そして疏水沿いの山科、蹴上、岡崎の各エリアは特に注目の地域。琵琶湖疏水の洞門や橋、南禅寺・水路閣、レンガ造りのポンプ室などのモダンな建築物からは、今も当時の歴史や面影を感じることができます。
かつて多くの人々が船に揺られ、行き交ったこの"水の路"。その路に沿うように走る"鉄の路"京阪電車に乗って、疏水の景色を巡ってみませんか。季節を映す水の流れとともに、古の人々の思いを訪ねながら。時には、新しい発見に驚きながら。

- 扁額
- 第1トンネル東口の扁額には、初代内閣総理大臣・伊藤博文による「氣象萬千(きしょうばんせん)」の文字が刻まれています。
びわ湖側から一つ目のトンネル、第1トンネルの東口は、三角の屋根を構えた堂々とした佇まい。第1疏水には、このトンネルを含め4つのトンネルがありますが、新しくできた諸羽トンネルを除くいずれの洞門も、洋風建築の玄関を思わせる意匠です。また、それぞれの洞門には、時の政治家らの揮毫(きごう)による「扁額(へんがく)」が掲げられています。
◎三井寺駅下車 西へ徒歩約7分



四ノ宮から日ノ岡にかけて約4kmにわたって疏水沿いに整備された遊歩道で、市民の憩いの場として親しまれています。春になると山桜を中心とした、およそ660本の桜並木と菜の花の競演が見事な花見スポットに。新緑や紅葉の頃も美しく、周辺の山々の景観と調和したたたずまいを見せています。
◎075-643-5405(京都市南部みどり管理事務所)
◎京都市山科区四ノ宮新開畑他
◎四宮駅下車 北へ、
京阪山科駅・JR山科駅・地下鉄山科駅下車 北へ、
地下鉄御陵駅下車 北へ徒歩約10分
蹴上付近は高低差の関係で舟の往来ができなかったため、疏水の建設とともに運用された水力発電所の動力を使い、台車に舟を載せて移動させるという手法が取り入れられました。これにより疏水の建設前は人馬での輸送が主だった大津-京都間の輸送技術が飛躍的に向上しました。
◎地下鉄蹴上駅下車すぐ

- ▲ねじりまんぽ
- 蹴上インクラインの線路下にあるトンネル(=方言で「まんぽ」)。強度を高めるために、レンガがらせん状に積まれ、ねじれている様子から「ねじりまんぽ」と呼ばれます。


明治時代の大事業であった琵琶湖疏水の建設について、当時の計画や建設の過程を紹介した資料などに加え、時代を動かした北垣国道や田邉朔郎などの人物に迫る展示が行われています。疏水工事の様子を描いた絵画、映像やパネルを通じて疏水が果たす役割などを知ることができ、様変わりした時代の流れをあらゆる角度から感じとることができます。
◎075-752-2530
◎京都市左京区南禅寺草川町17
◎地下鉄蹴上駅下車 北西へ徒歩約5分
http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007524.html
毎年10月に行われる天孫神社の祭礼・大津祭。目玉となるのは曳山の巡行で、同館では各町が保管する宝物が2カ月交代で展示されています。曳山のからくりを間近で見たり、先を争うようにお囃子の演奏体験をしたりと、地元の子供たちにも人気の施設。京都の祇園祭との関わりも深く、水の路でつながる歴史を感じられます。
月曜(休日を除く)、年末年始休館
◎077-521-1013
◎大津市中央1-2-27
◎びわ湖浜大津駅下車 南へ徒歩約10分