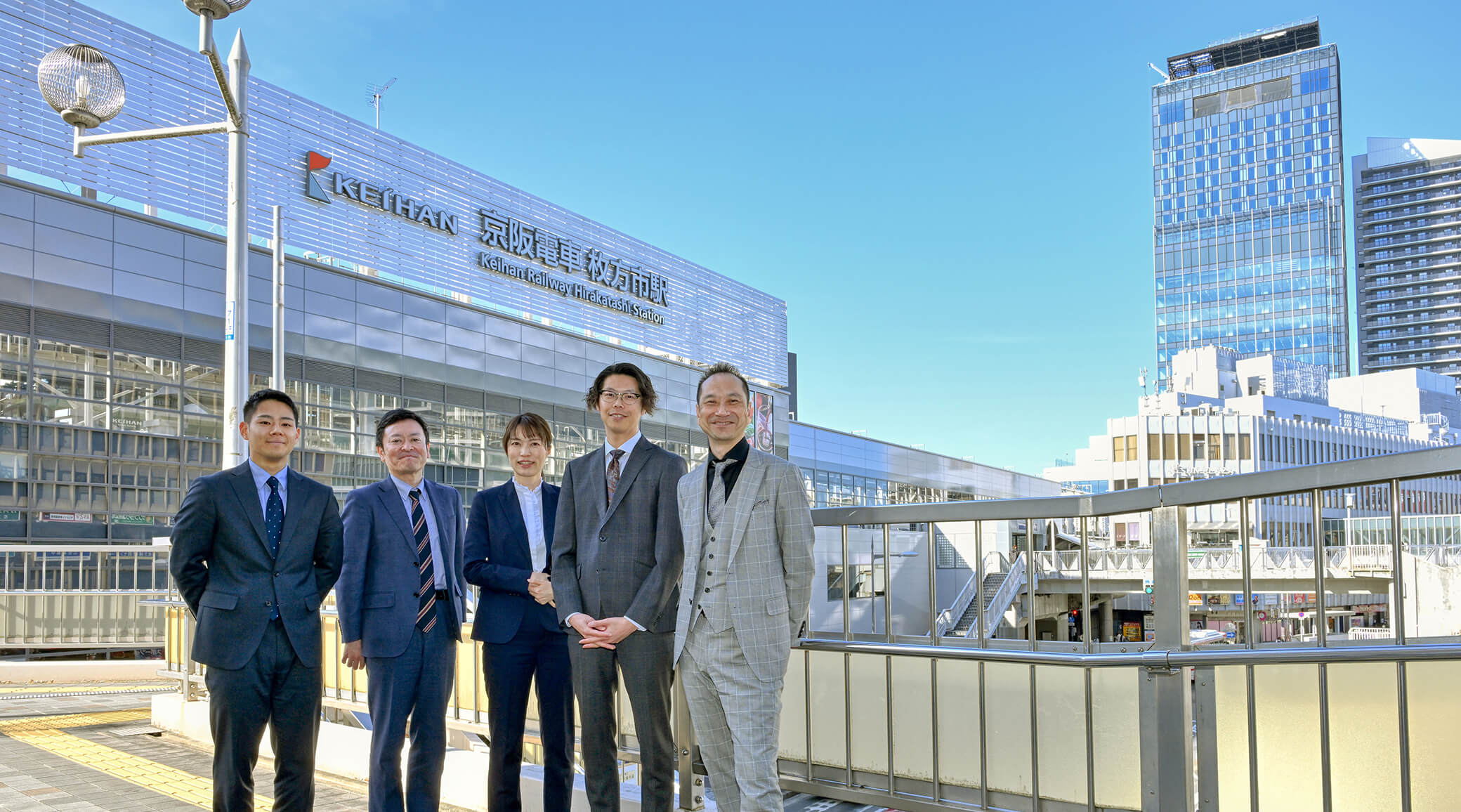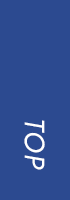枚方エリアマネジメントがスタート!
本再開発事業は、ハードの整備にとどまらず、ソフト面でも継続的なまちづくりを推進する「エリマネジメント」に取り組んでいることが特徴です。2021年1月に、枚方市駅周辺におけるエリアマネジメントや多様な人材が集う交流拠点の整備をめざして『枚方HUB協議会』が設立されました。「自分たちのまちは、自分たちでよくする」というこころざしにあふれたその活動内容とメンバーが思い描く今後の展望をご紹介します。
まちを育てる。
そんなまちづくりをめざす
林:第1回のトークでも話しましたが、この再開発は「まちを育てるまちづくり」を目標にしました。建物の竣工がゴールではなく、継続してまちを育てていくこと。目指すのは、ハードとソフト両面で魅力が高まり続けて豊かな暮らし方や働き方ができるまちへと進化し続ける枚方です。再開発組合でもハード面の整備計画と並行して、ソフト面のエリアマネジメントについても議論を重ねました。地域の方のまちに対する熱い思いもありましたし、この再開発事業をきっかけにエリアマネジメント組織を立ち上げられないか検討を始めました。京阪だけでソフト面のまちづくりが完結できるわけはなく、地域の方々や行政、専門家などと取り組まなければならない。まちづくりの議論の場であるエリアプラットフォームの設立を再開発組合とも協力して先導していきました。
関係者の皆さんに集まっていただく会場を設営するにも、講師の方をお招きするにも、ひとが動けば費用がかかります。そのコストをどう捻出するか? 頭を悩ませていたタイミングで、エリアプラットフォームの構築や未来ビジョン策定に関する国土交通省の補助事業が始まりました。これに申請すれば補助が出て具体的なアクションに繋げられるということで、枚方市や再開発事業に関わる事業者、地権者の皆さんにお声をかけて、みんなで協議する母体となる『枚方HUB協議会』を設立しました。それから3年間は、補助を受けながらワークショップやシンポジウムなどを開催してエリアマネジメントや公共空間の魅力向上事業などの検討を進めてきました。

京阪電気鉄道株式会社
取締役
山口 淳(やまぐち あつし)
それぞれの『枚方HUB協議会』への関わり
野村:私は生まれも育ちも枚方で、学生時代から枚方のまちづくりに関心を持って入社したので、再開発事業は念願の業務でした。2023年4月入社のため、『枚方HUB協議会』には最終年度に参加しただけでしたが、集まっている皆さんの盛り上がりがすごかったのが強く印象に残っています。
田中:私は、樟葉駅前のまちづくりにも関わっている関係から、くずはのエリアマネジメントにも携わっていますが先行する『枚方HUB協議会』に参加し、同じ枚方市ながら枚方市駅と樟葉駅前ではまた事情が違ったりするので、エリアごとに細やかに見ていくことの大切さを再認識しました。

京阪ホールディングス株式会社
経営企画室まちづくり推進担当
株式会社京阪流通システムズ 兼務
課長補佐
田中 又詞(たなか またし)
山口:私は京阪電気鉄道で経営企画部門の仕事についていますが、鉄道にとっても枚方市というのは沿線の中核都市で重要なポジションにあります。枚方がどれだけ活気づくかは非常に大事なことだとずっと思ってきました。この地で仕事をしていた期間もあったので、個人的に枚方に対する思い入れもあります。そんな中で『枚方HUB協議会』に参加することができ、ゆかりのある企業の皆さんと一緒に触れ合いながら、まちづくりに関して一緒に悩んだりしたのは、得がたく有益な経験でした。エリアマネジメントは鉄道グループにとっても欠かすことはできないテーマですので、これからも取り組み続けていきたいと考えています。

京阪ホールディングス株式会社
経営企画室まちづくり推進担当
野村 岳大(のむら たけひろ)
田中:林さんはエリアマネジメントを早くから学んでいたかと思うのですが、どのような経緯があったのですか?
林:たまたま以前にいた部署で、魅力ある大阪のまちづくりを推進する団体である「CITÉさろん」に参加する機会があり足を運んだことからです。そのサロンで大阪でまちづくりの第一人者として知られる大阪公立大学の嘉名光市先生と出会い、先生の講義を聞きたくて先生が座長を務めるワークショップにも2期4年参加しました。エリアマネジメントについて学んだのもそうした過程においてです。その後、まちづくりを担当する上司の下についたんです。そこでまちづくりに興味を持ち、色々と学んでいくうちに、せっかくだから業務に生かしていこうと思いました。それからは、何か提案する際にはまちづくりの視点で考えるようにしていきました。

京阪ホールディングス株式会社
執行役員
経営企画室まちづくり推進担当部長
<沿線開発、エリアマネジメント>
大浅田 寛
(おおあさだ ひろし)

京阪ホールディングス株式会社
経営企画室まちづくり推進担当課長
林 友美
(はやし ともみ)
エリアマネジメントとは?
一定のエリアを対象にして、民間主導のもと行政とのパートナーシップによって、住民・事業主・地権者等が関わり合いながら、主体的に進めるまちづくりのこと。「つくる」よりも「育てる」ことに主眼を置いている点が特徴です。取り組みを継続するための組織、事業、財源、公共空間を含む空間管理等もあわせて考えていくことが必要となります。

■今回の対談は枚方市駅周辺再開発チームが打ち合わせのために頻繁に利用したサンプラザ3号館の「肉の松阪」さんをお借りしました
毎回大盛況だった
まちづくりワークショップ
林:『枚方HUB協議会』初のワークショップを開催した際、協議会の参加者に「コロナ禍でもありますし、強制ではないので来られる方だけでも来てください」とお願いしていたら、テーマなども何も事前にアナウンスをしていないのにも関わらず50名ほど集まっていただいてすごく盛り上がったんです。あれは驚きましたし、感動しました。
田中:第1回はどういうことが話し合われたんですか?
山口:枚方の課題とか、枚方のここが好き!ここが嫌い!みたいなことでしたね。パナソニックさんや関西電力さん、三井住友信託銀行さんなど企業の方々、学生さんや枚方市の職員さんなど、年齢層も属性も違う皆さんが集いました。ちょうどコロナ禍が始まっていましたから、窓を大きく開けて換気しながら…。私も初めて尽くしの体験でしたが、すごく面白かったことを憶えています。
大浅田:若手もいれば、社用車でやってこられる役員もいて、参加者は本当に多様性に富んでいましたね。ワークショップや社会実験などを通じて、どんな枚方になって欲しいかという「未来ビジョン」をみなさんで模索した3年でした。
林:大盛況は2回目以降も続きました。ただ、やはりコロナ禍でしたので間にリモート会議を何回かはさみながらも、それでもワークショップはリアルじゃないと活発な場にならないので、できるだけリアルを心がけていました。1年目は3回実施し、2年目4回、3年目は2回、シンポジウムは3回実施しました。
野村:途中から参加した身ながら私が感じた手応えでいうと、部会で先生方に来ていただいて、お話を聞いたり、ワークショップを進めたりするんですけど、その準備の段階から先生方がすごく協力的なんです。「シナリオは、こんな感じでまとめたらいいんじゃないですか?」と打ち合わせの時にもアドバイスをたくさんしていただいて…。先生方をここまで乗り気にさせている大浅田さんと林さんって!?と驚くことが多かったです。どれほどの熱意を伝えたら、これだけお忙しい方々がここまで動いてくれるんだろう?と。正直、不思議でなりませんでした。体験した感想としては、部会ワークショップは大学の授業みたいで毎回すごく楽しかったです。ところで、私が参加した3年目には社会実験もスムーズに開催できたのですが初年度はどうだったのでしょう?

■まちづくりワークショップの様子
林:初年度はファーマーズマーケットにトライしました。ファーマーズマーケットを開催すると、地域の農家さんと住民との間にコミュニケーションが生まれたり、この土地の野菜って美味しいって発見がエリアの愛着につなかったりすると知り、最初はファーマーズマーケットが良いのではと考えていました。ただ、ある程度想像はしていましたが、やはり協力していただく大学や行政もハードルが高かったですね。公共空間の魅力向上につなげたかったのですが、公共空間の使用許可って厳しくて。前例やルールに縛られて、最初から全部ダメみたいな協議ばかりで闘い続けましたね(笑)。
野村:そうだったんですね!私が経験した3年目は苦労もありましたけど、申請を出したらそんなに返されることはなくて。やはり1年目、2年目で実績を積んだからこそ3年目はエリアマネジメントが大事だということ、公共空間を使うことに意味があるということについて理解がだいぶ進んでいたのかなと今の話を聞いて感じました。


■枚方市駅高架下を歩きたくなるような空間にするための可能性を探るファーマーズマーケット
未来ビジョンとは?
エリアがめざす方向性や将来像を定め、実現に向けて必要な取り組みや役割について示すもの。枚方市駅周辺エリアでは、『枚方HUB協議会』で2024年を起点とした10年後のめざす姿を考えました。エリアの特性や課題を探り、どんなエリアになってほしいか、そのために何が必要かといったことを意見交換して、課題解決をしながら将来像を実現するにはどうしたらいいのかを考えました。
3年間の活動を振り返って
大浅田:制度とか法令に対してどうすれば実施できるか、みんなで知恵を絞ってきた3年間でした。田中さんや山口さんは参加してどう感じていましたか?また、今後の課題や展望についてはいかがでしょう?
田中:冒頭、私はくずはのエリアマネジメントにも関わっていると話しましたが、前部署では決算資料や株主通信を作成する立場にもありました。そこでは必ず「ハードの整備に留まることなく、まちを育てるソフト面にも取り組んでいく」という文言が入っていました。つまりハードだけ、ソフトだけではまちづくりを成功に導くのはなかなか厳しい。その点において、枚方はハードとソフトが両方バランスよく、両軸で前進してるのが素晴らしいなとワークショップの盛り上がりを見て思いましたし、ハードとソフトの相乗効果を強く感じます。ただ、枚方市駅周辺は広域なまちづくりなので、これから先の舵取りはきっとすごく難しい。まちをつくり上げていくのは民間だけでは無理ですし、行政だけでも無理です。みんなが一緒の方向を向かないとまとめられないので、そこの難易度の高さを今から痛感しています。

山口:30年前に枚方市駅は高架駅になって、行政がつくったデッキでビルがつながって一見便利になりました。でも、こうした開発ではグランドレベルの人の往来が減っていき、結果的にまちの活気が失われていきがちなんです。先ほどファーマーズマーケットを開催しようとした際に公共道路の使用を巡って苦戦した話題が出ましたが、実は京阪電鉄でも以前から枚方市駅の周辺道路を使って何かできないか?と枚方市に働きかけたりしていました。でも、やっぱり却下となるんですね。それだけに『枚方HUB協議会』が挫折を繰り返しながらも実現していったのは非常に大きな前進です。私は、“歩いていて楽しい”というのが魅力的なまちの必須条件だと思っています。そのためには、やはり地上を歩いて楽しい工夫が必要です。枚方市駅周辺となると範囲も広いのであと何年かかるかわからないですが、いろんな発見ができる仕掛けをまだまだつくっていく必要があると思っています。田中さんのいう通り、エリアマネジメントってきっとここからが本丸でしょう。住んでいる人にもっと好きになってもらうのも大事、よその土地から来てみたいと思ってもらえることも大事、さらにリピーターになってもらうのも大事、それらが影響を及ぼし合って結果的にまちへの経済メリットになることも大事。枚方がそんなまちになるために、あと何年かかるかわからないけれど、諦めちゃいかんと改めて自分自身を鼓舞する思いでいます。
林:山口さんが語っていただいたところってとっても大事なポイントだと思います。エリアマネジメントの概念は20年前くらいに聞くようになったのですが、当時はなかなか社内でそんな議論もありませんでした。ところが今、みなさんがエリアマネジメントの大切さを語られていて、すごく変わったんだなと実感しています。そういう意味で、社内のエリアマネジメントに対するとらえ方の変化を感じますが、『枚方HUB協議会』の動きがきっかけの一つになったのであれば感慨深いです。
田中:もう1点付け加えますと、協議会って全国で組成されていても機能していないところがけっこう多いんですね。ところが枚方はちゃんと機能していて、参加者もまちづくりビジョンを作るためにしっかり活動されていた。そのような協議会自体が稀有な存在だと思います。自分自身くずはでも同じような活動をやっていますが、『枚方HUB協議会』ですごく勉強させてもらいましたし、私にとって力強い支えになっています。


■枚方市総合文化芸術センターで行われた『枚方HUB協議会』シンポジウムの様子