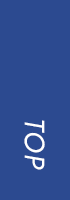なぜ、枚方だったのか?
大浅田:枚方市駅には社有地があった関係で、そこの活用をどうするかという点については30年以上も前から社内で何度も議論され、計画が検討されてきました。枚方市は人口約40万人の中核市で、京都と大阪を結ぶ京阪本線のほぼ中央にあり、枚方市駅の乗降人員はコロナ禍前で約9万6,000人と京阪電車にとっては3番目に多いお客さまの数を抱える重要な駅です。支線の交野線との乗り換えに加えて、バスの1日あたりの発着便数も約1,000便、いわば郊外交通の結節点です。それだけに、いかに枚方市の魅力向上につなぐ自社開発ができるかは京阪グループ全体のミッションと捉えられていました。
林:枚方市をデータでみると、この30年だけでいえば人口はそんなには減ってはいないんですね。ただ、20~39歳までの年齢層での人口を比べると激減していて、大学生に至っては45%くらい減っています。このまま若い世代や世帯の流入のないまま人口減少へと転じていけば、まちは確実に活力を失っていきます。京阪グループとしての長期的な経営戦略「沿線再耕」に照らしても、枚方においてこれからの時代にふさわしい開発を駅を起点にどう始めるかは、沿線のその他の駅周辺開発をどのように位置付けるか、という意味でも非常に重要でした。
寒川:私は大阪出身で、京都に先祖のお墓がある由縁で幼い頃より家族全員で京阪電車をずっと使っていました。私自身にその記憶はないのですが、枚方市駅って昭和の頃に1度再開発をしているんですよね?
大浅田:はい、そうですね。1969年に公布・施行された「都市再開発法」に則って55年前に高架駅にして踏切を無くし、駅前にロータリーを作って、駅前ビルとペデストリアンデッキ(高架型歩道)でつなぎました。モータリゼーションに合わせた設計で、全国の都市でそうした設計が採用されました。しかし、それは55年前の最先端の姿なんですね。そのまま時が止まっている状態が続いており、老朽化とまではいかないけれど様々な部分で時代とそぐわなくなってきていました。そこを新陳代謝させていかなければならないし、それによって若い世代の流入が減っている等の枚方市の課題にも応えていく必要があると考えたのが、今回の再開発の起点です。

京阪ホールディングス株式会社
執行役員
枚方市駅周辺開発室 部長
大浅田 寬(おおあさだ ひろし)

■高架化以前の枚方市駅